
劇的な変化と不確実性に満ちた現代社会において、未来を切り拓いてきたトップランナーは何を見据えているのか。本連載では、PwCコンサルティングのプロフェッショナルとさまざまな領域の第一人者との対話を通じて、私たちの進むべき道を探っていきます。
第11回は、イノベーション・マネジメントや若手人材育成のエキスパートである金沢大学 融合研究域 融合科学系 教授 金間大介氏を迎え、PwCコンサルティング合同会社で公共事業部の福祉・社会保障イニシアチブをリードするディレクターの東海林崇とマネージャーの池田真由が、労働力減少問題の課題先進業界である「福祉・介護」業界における今後の人材獲得戦略を議論しました。

(左から)東海林 崇、金間 大介氏、池田 真由
参加者
金沢大学 融合研究域 融合科学系 教授
東京大学 未来ビジョン研究センター 客員教授
一般社団法人WE AT 副代表理事
一般社団法人日本知財学会 理事
金間 大介氏
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 ディレクター
東海林 崇
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 マネージャー
池田 真由
※対談者の肩書、所属法人などは掲載当時のものです。本文中敬称略。
止まらぬ高齢化、介護職員57万人不足の未来
金間:
ここ最近、「人口減少社会」という言葉をよく聞くと思います。実は、生産年齢人口が減り始めているのは、はるか前の1995年からです。もう30年間ほど生産年齢人口が減り続けていて、その減少数は約1,500万人。これはなんと、現在の台湾の生産年齢人口と同規模の数字です。さらに、働く人の高齢化も進んでいる。色々な業界で「人手不足だ」と言われているのが当然の状況かと思います。
東海林:
介護の世界でも、だいぶ前から人材不足が叫ばれています。厚生労働省の推計1によれば、現在の介護職員数を基準とした場合2026年に約25万人、2040年に約57万人が不足すると言われています。そもそも、現在の介護職員数が維持されるかについても非常に危ういところです。隣接領域である教育の現場でも、既に教員の不足と過重労働が深刻化しています。介護・福祉業界がサービス提供を維持するためには「今ある土台さえ崩れる可能性」を前提として考える必要があります。
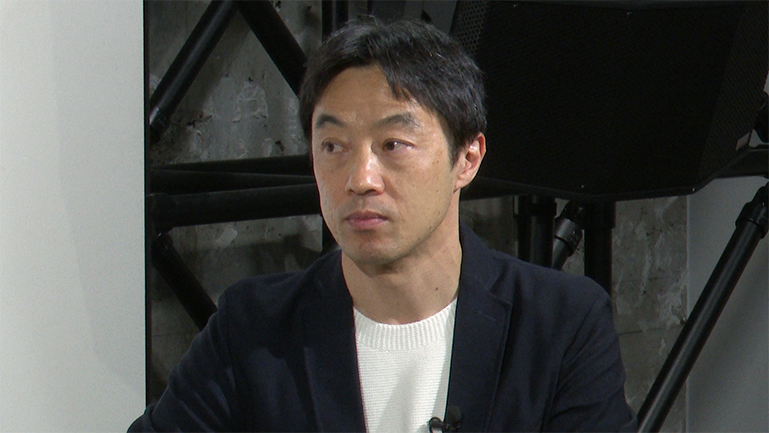
金沢大学 融合研究域 融合科学系 教授 金間 大介氏
介護業界の変革期―経営者に求められる「考える力」―
東海林:
実は、これまでの介護・福祉業界は、他の業界と比べると、業界の外への転職者数があまり多くはなかったんです。ところが最近、転出者が増加している。一つの背景として、民間企業の参入によってガバナンスが問題視されはじめたことがあるように思います。金間先生の見解はいかがでしょうか。
金間:
2000年代くらいの学生は、介護業界に「ブラックの代表」のようなイメージを持っていた気がします。ただ、最近の学生と接しているとどうやらそうでもないようです。
東海林:
若者の視点では、「どんな組織文化があり、どんな人と働けるか」も仕事選びの上で大事なように感じますね。
金間:
介護事業所の経営者と話すと「自分の組織を辞めてしまわないか」ということまでが関心の対象で、「介護業界を辞めてしまわないか」ということにはまだ十分な注意を払っていない印象を持ちます。若者の立場から見ると「同じ業界の中でより評判の良い法人に行くか、思い切って他業界に移るか」のような選択肢が広がっている状況かなと思います。
東海林:
「介護・福祉業界は誰が経営しているのか」に着目すると、社会福祉法人等の非営利法人が多く、法人規模としても小さいところが多い印象があります(図表)。経営主体として社会福祉法人の占める割合が多いのは特別養護老人ホーム(以下、「特養」)です。地域の中に非常に多くの小規模な法人が存在していて、代々その土地で経営している法人が多いのが特徴です。
図表:福祉・介護業界のサービス提供主体

厚生労働省「令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況」を基にPwCが作成
東海林:
介護保険制度が始まった2000年より前から経営をしている古参事業者が多いですよね。以前は行政から措置費を受け取り、事故なく運営すればOKという時代でしたが、今は経営者がガバナンスを含め、経営戦略を立てることが必要になってきています。こういった「考えて動ける」経営者はどれほどいるのでしょうか。
金間:
2000年頃はまだ高齢者の数が少なく、原則として家族が高齢者を支えた上で、介護サービスを利用する世界観でした。そのため、法人はあまりサービスを差別化する必要性がなかった。逆に言えば、どこでも同じサービスが受けられる状況でした。ところが今、高齢者の数が増えて支える側の人間が減り、付加価値が求められて徐々に差が出てきています。
東海林:
特養を経営する上で、国で定められた基準のことをするには経費がかかるなど事業展開のリスクが高いと感じている経営者も多いように見えます。今後は、在宅系のサービスや介護業界以外への展開などを考えることが経営成功の鍵になるはずです。
金間:
訪問介護は、データにも表れているように、営利法人も参入しやすいところというイメージがあるのではないでしょうか。知見の広い理事長や経営者はデジタル技術の駆使にもアンテナを張っていて、「スタートアップを作ろうと思っている」などのお話も聞きます。
東海林:
DX導入にも施設によってかなり差がでていますね。
金間:
介護福祉法人の話をしているのに、「ビジョン」「ミッション」「パーパス」「ガバナンス」のような言葉が並んでくることに、時代の変化を感じます。それに伴い、働く皆さんの経験の積み方も多様になっているのではないでしょうか。例えば「自分はデジタル領域に関心があるので、訪問介護への配属を希望する」などと言えるようになってきている。これは、今日のテーマである「人材獲得競争」にも影響を与える要素だと思います。
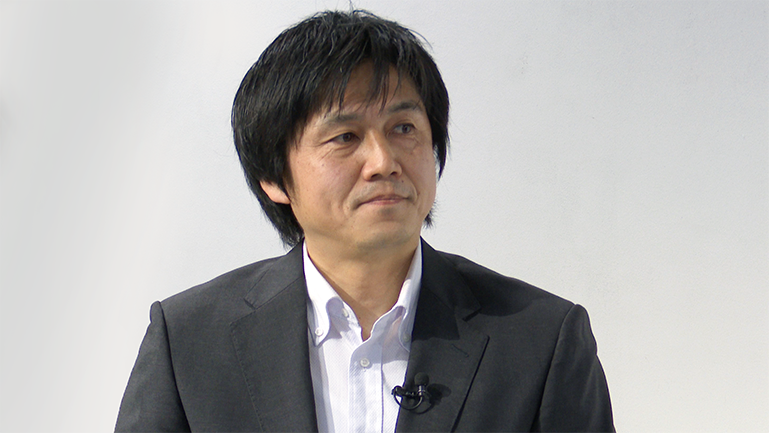
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 ディレクター 東海林崇
地域限定から全国へ、拡大する介護業界の人材獲得範囲
東海林:
最近は人材が多様化していますが、福祉・介護分野での働き方にはいくつかの傾向があると考えています。1つ目が「遠隔で働くのが難しい人が多い」こと。採用側の視点では、地域の中で人材獲得をする必要があるということになります。次に「はじめから専門的知識や技術を持つ必要はなく、成長する中で身に付ければよい」こと。これは参入障壁の低さにもなる一方、入職後に身に付ける仕組みを整えないと、虐待や事故につながりやすくなります。最後に「残業が少ない」こと。過重労働であるという誤解を払拭する必要があります。また、離職が多い事業所の特徴には「人材の成長プロセスが明確ではないこと」「教育制度が整っていないこと」「賃金や福利厚生などの待遇が悪いこと」があります。先生のお考えも聞かせてください。
金間:
おっしゃるとおり、かつては地域の中での雇用が基本でしたが、最近は「地域を超えてでもこの法人で働きたい」と考える人が増え、人材獲得競争の範囲が広まっているように思います。残業の少なさは、労働環境を改善する努力の成果ではないでしょうか。離職については、システムというより、やはり人間関係やコミュニケーションの課題が多い気がしますね。

PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 マネージャー 池田真由
介護業界の未来を築く鍵とは?
金間:
私のゼミ生が全国の社会福祉法人等の勤務者を対象に行ったアンケート調査によれば、介護福祉士や社会福祉士等の有資格者は、無資格者に比べて利用者のことを思って主体的な行動・価値提供をしていることが分かりました。ところが評価・報酬、居心地の良さなどに代表される働きやすさについては、無資格者の方が感じているという結果になっています。「介護の世界で頑張りたい」と思い資格を取得する方が報われるような環境づくりが必要だと感じます。介護職の方には、私たちは必ずと言っていいほどお世話になると思います。つまり、介護職の方がどう行動するかで私たちのウェルビーイングも変わる。介護職の方が生き生きできるような世界にすることで国民のウェルビーイングが少し向上するという信念の下、どう変化を起こそうか本気で考えています。
東海林:
国は「山脈型キャリアモデル」という人材育成の仕組み作りを打ち出しています。専門家のような人材に加えて、マネジメント層など、複線型のキャリアラダーを作り、裾野も広くしましょうという方針です。
金間:
大企業の中でも言われる話ですね。そもそも、登山するモチベーションを得ることが難しいと言われています。
東海林:
そして、この山脈型キャリアモデルを描ける法人や事業者は多くないということもあります。地域の中で人材確保を達成するため、複線型のキャリアラダーを、1つの事業所ではなく、地域全体の中で考えるべきではないでしょうか。
金間:
最近は法人の経営力に格差があることから、地域内で1つのコミュニティとしてまとまりをもって人材確保をすることのハードルは高いように思います。
東海林:
経営力のある法人が、そうでないところをどう吸収し、地域を再編していくかという視点も必要ですね。介護の現場で、専門職の人がモチベーション高く働けるような環境を作れる経営者が出てくると、介護業界の人材確保にとっての処方箋になると感じました。
金間:
先ほどお話ししたように、1つの大きなグループ法人の中には、スタートアップを起こそうとしている人もいる。そういった人が業界を引っ張る構造になると考えています。
東海林:
介護業界では、国が定めた報酬の単価に沿った人員確保をしなければならないという制約もある。業界の再編にあたり、行政がどう関わるかも大事な視点だと考えますが、いかがでしょうか。
金間:
生産年齢人口が減少する中で、経営統合が起こるのは当然のことだと思います。この分野でのM&Aはノウハウがあまり蓄積されていないため、行政は、誰も困らない形で協業を支援する必要があります。また、経営統合だけではなく、経営の効率化も必要です。私が見る限り、介護・福祉業界を選択する若者は、そこまで出世意欲が高い訳ではない一方「人のために何かをしたい」という気持ちは強い印象があります。そういった気持ちを汲んであげられるような現場の仕組みやガバナンスをすることが大事だと思っています。
金間:
介護業界はマニュアルが前提の仕事です。提供するサービスも9割方は「決められた正しさ」のようなものがある。残りの1割に働く人自身の思いを乗せることができるかが、マネジメントのポイントになるだろうと思います。
池田:
コンサルタントの立場から見ると、介護・福祉業界はビジネスの根幹である圧倒的ニーズがあるにも関わらず、うまく回りきっておらず、ノウハウ提供の喫緊性が高いことにやりがいがあると思いました。自身が就活生だった時のことを思い返すと、志望する就職先として、業界の前に企業名が立つことが多かったように思います。人気の事業所が増えることで、メゾレベルで業界が成長し、業界自体の魅力度が高まる可能性を感じています。これは、金間先生のおっしゃっていた経営主体やスタートアップの話とつながるのだろうなと考えました。
金間:
そのとおりですね。最後に、コンサルタントの方には「個人戦を戦える者のみがチームに貢献できる」という言葉を贈らせてください。本当の意味でチームや社会に貢献できる人は、個で戦える人だな、と常々思うようになってきました。今日の話で言うと、専門資格を取得した介護職の方などには、地域に貢献し、引っ張っていけるポテンシャルがある。そういった方が気持ちよく働けるような職場づくりが必要だと考えています。
1 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」より(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf)



