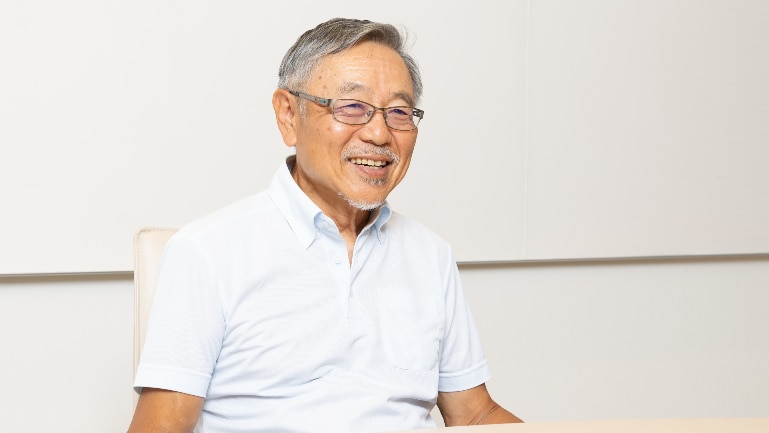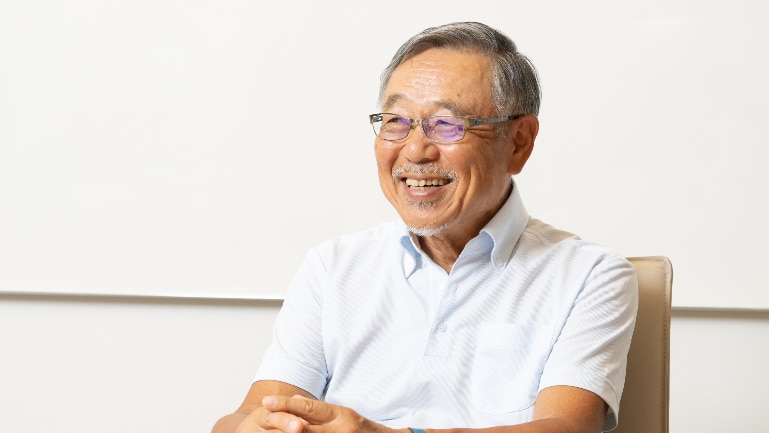{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
本シリーズの第1回では、食料安全保障に関する日本の現状や課題について概説するとともに、これからの日本に必要な食料安全保障政策について、PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)なりの提言を述べました。
第2回となる本稿では、当社の認識や提言について、専門的な知見やデータを踏まえて検証・深耕すべく、外部からの専門家をお招きして対談を行いました。
お招きしたのは、元農林水産省(以下農水省)官僚という立場から、現在の日本の農政に対する厳しい姿勢で知られ、テレビや新聞など各種報道はもとより衆議院の農林水産委員会でも意見を求められる山下一仁(やました・かずひと)氏です。
食料需給の世界的な現状から、日本の農政の課題、昨今の報道姿勢なども含めて舌鋒鋭く語っていただき、私たちとしても多くの気づきを得る機会となりました。
山下 一仁(やました・かずひと)氏
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
RIETI(独立行政法人経済産業研究所)上席研究員(特任)
1955年岡山県生まれ。77年東京大学法学部卒業後、農林省(当時)に入省。農林水産省でガット室長、欧州連合日本政府代表部参事官、農林水産省地域振興課長、農村振興局整備部長、同次長などを歴任した後、2008年に農林水産省を退職。82年ミシガン大学応用経済学修士、行政学修士。05年東京大学農学博士。
『日本が飢える!食料危機の真実』『バターが買えない不都合な真実』(幻冬舎新書)、『農協の大罪』(宝島社新書)、『農業ビッグバンの経済学』『国民のための「食と農」の授業』(日本経済新聞出版社)、『「亡国農政」の終焉』(ベスト新書)など著書多数。
齊藤 三希子(さいとう・みきこ)
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
国内SIer、日系シンクタンク、外資系コンサルティングファームを経て現職。
外資系コンサルティングファームを中心に15年にわたりサステナビリティに係るコンサルティング経験を有し、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)やバイオ・トランスフォーメーション(BX)関連の講演や執筆も多数。
地域資源を活用した持続可能な地域モデルの構築や、Agri-Food Tech、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、バイオエコノミー、SX、食料安全保障などに係る事業の創出に幾度となく携わる。
齊藤:
昨今、日本の食料安全保障について、穀物をはじめとした価格高騰による「買い負け」や、海外からの物流途絶による供給難の両面から不安が高まっています。山下先生は最近の動向をどのようにご覧になっていますか?
山下:
日本の食料事情は近年、急激に悪化したように言われていますが、もともとここ10〜20年の間は一貫して悪い状況が続いていて、特に大きな変化があったわけではありません。ただ、世界情勢の変化を背景に危機感を煽る人が増えてきたため、一般の方にも不安が広がってきたのでしょう。
齊藤:
危機感を持つのは結構なことだけれども、決して最近になって急に悪化したわけではないということですね。
山下:
先ほど指摘された2つの側面については、それぞれ別個に論じる必要があります。まず価格高騰について言えば、実際には、世界的に見てそこまでの危機的状況とは言えません。USDA(米国農務省)が出しているデータによると、三大穀物と呼ばれる米・小麦・トウモロコシ、それらに次ぐ重要度を持つ大豆の価格は、この100年、150年間という長期的な視点で見ると、実質的な価格はずっと低下しています。
もちろん、突発的に上がる時期もあって、例えば1973年に、当時は小麦の輸出大国だったソ連の大量買い付けによって高騰しました。2022年にはウクライナ侵攻の影響で小麦の国際価格が史上最高値との報道もありましたが、それはノミナル(名目上)なもので、リアルの価格だと73年当時の半分もないほどです。
齊藤:
2008年の「洞爺湖サミット」でも、ロシアを加えたG8(主要8カ国首脳会議)で世界の食料安全保障について議論されました。当時、米国の政策変更でトウモロコシをエタノール原料にすることによって価格が高騰して、代替性のある米や小麦、大豆にも波及したためでしたが、現在ほどの危機感は感じられませんでした。
山下:
2008年当時、穀物価格は3~4倍に跳ね上がりましたが、日本の消費者物価指数は2.6%しか上昇しませんでした。なぜかというと、私たちの食生活では原料農産物の比率がすごく低いのです。原料よりも加工や流通、外食に対価を払っていて、これは日本だけでなく、先進国はみんな同様です。
ところが、途上国の人々は所得の大半を食費、それも加工食品や外食ではなく、小麦から作られるパンや米に使っています。それらの価格が3~4倍になったら、とても買えなくなってしまう。だから飢餓が生じます。
一方、日本の場合は輸入総額のうち穀物・大豆は1~1.5%しかなく、所得水準や経済力の高さを考えれば、価格が10倍になってもまだ買えるわけです。そのため、日本で飢餓が起こることは考えられません。
齊藤:
とはいえ、世界的な人口増を背景に、「このままでは食料が不足する」との危機感を持つことは大切ではないでしょうか?
山下:
確かに、1960年から現在までに人口が2.5倍と爆発的に増えていますが、その後は人口の伸びは鈍化します。どこまでも増えていくわけではないのです。一方で、穀物の生産量は小麦が3.4倍、米が3.5倍と、人口の伸びを上回っています。農地面積が頭打ちと言われますが、ブラジルやアフリカにも相当の未開拓な農地があり、まだまだ増やせる余地は多いのです。
齊藤:
ただ、今回と2008年とでは状況が異なると思っているのが、冒頭で述べた2つ目の側面です。ウクライナ侵攻を目の当たりにして、シーレーン(海上交通路)の崩壊によって食料が輸入できなくなるという危機が現実味を帯びてきているかと思います。
山下:
今、私たちが懸念すべきはそちらの側面でしょう。いくら穀物価格が高くなっても日本が買い負けることはありません。しかし、シーレーンが破壊されて日本に届かなくなるというのはリアルな危機です。いかに海外からの輸入に頼らない状況をつくるかが、今日の食料安全保障の本質だと思います。
ところが、最近では「日頃から穀物輸出国と仲良くしよう」とか「輸入先を多角化しよう」という論調が出てきています。いくら輸出国と仲良くしても、シーレーンが破壊されればモノが届かないのですよ。
科学的なエビデンスがない意見に惑わされてしまうと本質を見失ってしまいかねないので、しっかりとしたデータをもとに、今、何が必要なのかを考えることが大切だと思います。
齊藤:
昨今の地政学リスクの高まりを踏まえると、食料安全保障の根幹は国内の食量生産を増やすことだと思っています。しかし、国の政策を見ていると、山下先生もご指摘のように、国内の生産を増やす施策よりも、海外からの輸入を安定化することに注力しているようで、正直なところ不安を感じています。
山下:
私の計算だと、もしシーレーンが崩壊すると、終戦直後の配給量から換算して年間1,600万トンの米が必要になります。ところが現在は減反などで米の生産は700万トンを切っていて、備蓄を含めても危機が起きた時に必要量の半分以下しか供給できないのです。
終戦直後の配給量とは一人当たり2合3勺で、現在の米の消費量からすれば多いと思うかもしれませんが、副食がほとんどなかったため、こんなに米を食べてもすごくひもじい思いをしたんです。現在の備蓄量を考えれば、2合3勺の配給で半年は持つでしょうが、半年過ぎたら国民1億2,550万人全員飢えて死ぬみたいな計算になってしまうわけですよ。全然足りてないわけです。
齊藤:
恐ろしい計算ですね。シーレーンが崩壊しても食料供給を維持するためには、やはり先進的な技術も取り入れながら、食料生産量を増やすことが急務になります。その点で先生が期待されている取り組みや技術はありますか?
山下:
私が一番注目しているのは、ゲノム編集です。10年ほど前に米国で開催されたゲノム編集に関する会議に出席しましたが、まだ日本人は少なかったですが、中国人の研究者がとても多いことに驚きました。中国では国内での食料生産の必要性を重視していて、政府の命令で若くて優秀な人材が米国の大学や研究機関に留学して学んでいるのです。
齊藤:
山下先生がスマート農業(ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業)よりもゲノム編集に期待される理由は何でしょう。
山下:
スマート農業にも期待しないわけではありませんが、効果がインクリメンタル、つまり階段を一段ずつ上がっていくような増え方になります。それに対し、ゲノム編集はエレベーターで一挙に10階、20階まで上がるような、飛躍的な効果が期待できます。
というのも、ゲノム編集は遺伝子操作によって人為的に突然変異を生じさせることで、例えば1ヘクタールあたりの収穫量を2倍や3倍、10倍にすることが可能なわけです。
より少ない資源で、より多くのものを作る「プロデュース・モア・ウィズ・レス」が世界の潮流で、それが大きく期待できるのがゲノム編集だというわけです。
齊藤:
国土が狭く、資源がない日本にとってすごく有効な手法だと思いますが研究テーマとしてなかなか賛同を得にくいのが現状かと思います。
山下:
ゲノム編集は、お金がかからない技術なので、中小企業のスタートアップでもできるし、大学の研究室でもできる。ゲノム編集キットがあれば個人でもできます。あとは、消費者からの理解を得られるような、丁寧な説明が重要ではないでしょうか。
齊藤:
日本でも筑波大学の研究グループがトマトのゲノム編集、京都大学・近畿大学が真鯛やトラフグのゲノム編集で成果を挙げていて、国内だけでなく海外でも話題になっているくらいですから、使われているゲノム編集技術の安全性を説明し、政府もぜひ、後押ししてほしいものですね。
齊藤:
ここからは、日本の食料生産を支える農政についてお聞きしていきます。先ほど山下先生が指摘されたように、日本の主食である米の生産量は減反政策によって減少を続けています。なぜ日本の農政は、米の生産量を増やす方向には動かないのでしょうか?
山下:
米は日本人の主食であり、日本の風土にも適した農作物です。それなのになぜ、政府が生産量を増やそうとしないのかというと、1つには経済学的な理由があります。
工業製品では、例えばテレビの価格が安くなったから一家に2台、3台置こうというように、購入量が増えます。これに対して、食料や農産物の場合には胃袋が一定なので、米の価格が下がったからといって購買量が大きく増えるわけではありません。これを農産物の需要は非弾力的、インエラスティックと言います。
齊藤:
「豊作貧乏」という言葉があるように、野菜の生産量が増えると、市場でそれを売らないといけないために価格を下げないといけなくなる。それが非弾力的というわけですね。
山下:
その逆を狙ったのが減反政策で、例えば供給量を10%減らすと、価格が10%以上、場合によって50%くらい上がるため、農家にとって有利なわけです。農協にとっても、販売額に応じた販売手数料が得られるわけですから、やはり減反政策による米価上昇はメリットがあります。
齊藤:
近年では、日本国内で米の需要が減っていますから、それでも高い米価を維持するためには、さらに生産量を減らそうとしているわけですね。
山下:
重要なのが、米価を上げたために兼業農家が滞留していること。米価を上げると、コストの高い小さな兼業農家でも生産を継続することができます。その結果、零細な兼業農家が多数を占めていることが、日本農業の最大の問題だと思っています。
実際のデータを見ると、現在、日本の農家の50%強が米農家ですが、農業生産額全体に占める米の割合は16%です。それの何が問題かというと、小規模な兼業農家が多数を占めることで、米農業の生産性が低下するからです。農業の生産性を高めるには大規模化することが基本です。結果として、日本の米作は生産量だけでなく生産性でも海外に後れを取ってしまっているのです。
齊藤:
食生活の変化や高齢化に伴い、日本における米の消費量は、1962年をピークに減少傾向となっています。ピーク時には1人あたり年間118kgの米を消費していましたが、2021年には半分以下の51.5キログラム1になっています。
国内需要の減少に伴い、2022年の主食用米等生産量は675万t2と、ピーク時(1967年1,445万トン)の半分以下3となっています。
一方、気候変動や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大、ロシアのウクライナ侵攻などの影響もあって、小麦や大豆などの穀物価格が高騰したことより、世界的には米の需要が増加しています。USDA(米国農務省)のレポート4によると、2021年の世界の米消費量は2019年比で4.5%増加しています。
2022年は、パキスタンの大洪水による影響もあり、世界的に米の収穫量の減少が見込まれており、さらに食料安全保障への危機感が増しています。
世界では今この時も、食べるものに困っている人(飢餓人口、栄養不足人口)が約12億人もいます。日本は人口約1.2億人なので、その10倍もの人々が生存の問題に直面しているわけです。毎日不自由なく食べられることは、決して当たり前のことではなくなっているかと思います。
そんな中、米の生産量の抑止につながるような政策を実施しているのは、世界的な潮流から逆行していますね。
山下:
そもそも食管制度や食糧管理法は、戦中・戦後の食料供給がひっ迫した時期に、農家から米を強制的に買い入れて消費者に公平に安く配分するという配給制度を維持するため、つまり消費者目線の制度・立法でした。それが、高度成長時代になって、農家所得の向上という旗印の下で、政府が農協を通じて米を買い入れる際の価格、“生産者米価”を上げることが政治運動化していきました。1960年代から70,80年代と、農協を中心に「農民の春闘だ」と言って米価を上げろという運動をずっとやってきたことで、いつしか目的が変質していったのです。
齊藤:
農協の解体・改革については以前から言われてきましたが、なかなか進んでいないのが現状かと思います。
現在の農水省の役割からして、先進技術の導入や輸出拡大といった方向には動きにくいところがあるかもしれません。日本の農業の経済合理性を高めるためにも、産業創出や育成を担っている経済産業省との役割分担なども必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
山下:
最近、ある食品メーカーの取締役会で講演した際に、国土面積が九州ほどしかないオランダが、農産物輸出量で米国、ブラジルに次ぐトップ3に位置しているという話をしました。そのとき「なぜオランダが農産物輸出国になれたのか」との質問に対し「農業省を廃止して経済省に統一したから」と回答しました。
農業も工業も利潤を極大化するというところでは全く同じです。
例えば、農家に対する技術的指導は、日本だと農協や自治体の担当で、米国やオーストラリアでも行政サービスの一環ですが、オランダはそれら全てを廃止して、民間のコンサルタントに任せています。このため、ある程度の技術水準があって、収益を上げている農家だけが、より高い技術指導を得ようとコンサルタントに対価を支払います。それができない農家は淘汰され、結果として国全体で農業生産がレベルアップできたのです。
このように、農業も工業も同じ経済活動という視点から発想することが、日本の農政を変える第一歩になるのではないでしょうか。
今回の対談に際しては、齊藤ディレクター以外にも、オンライン参加を含めてPwCコンサルティング合同会社 Agri & Food Initiativeメンバーが同席しました。対談の最後に各メンバーから山下先生への質疑応答が行われたので、その模様を紹介します。
Q1:上敷領
日本でも農業生産性を高めるため、農地バンク制度など農地集積に向けた施策が進んでいますが、なかなか利用が進んでいないようです。何かドラスティックな解決法はないか、ご意見をお伺いできますか。
山下:
兼業農家が農地を貸し出さない理由は大きく2つあります。1つは、欧州のように宅地と農地のゾーニングが明確でないため、いつでも農地を宅地に転用できるから。もう1つは、先述したように米価が高いから。大規模専業農家に貸すよりも、小規模でも自分で米を作った方がお金になるからです。
ですから、ドラスティックにやるなら減反をやめて米価を下げればいい。実際、初期に農地バンクで流動化する量が増えたとされたのも、米価が下がった時です。
米農家の収益は、1ヘクタールの規模だと明らかにマイナスですが、20~30ヘクタール規模の農家だと年間所得が1,500万円に達するケースもあります。1つの農家に広い土地を集約して任せれば、そのくらい稼げるわけですから、それを地代として農地や水路の維持管理費として農地の出し手に分け与えることで、地域の農業資源を維持できます。今のように、みんなが平等に農業収益がマイナスという状況を脱して、大規模専農家が農業を行い、農地の所有者は地代収入で農業のインフラを整備するという農村社会にしていくべきでしょう。
少し余談になりますが、民俗学者として知られる柳田國男は東大法学部から農商務省に入りました。彼の主張というのは、農家が多すぎるから、今でいう兼業農家を減らして主業農家だけで生きていけるようにしようというものでした。この発想が戦後まで続き、1991年の農業基本法につながりました。
Q2:川原
ビジネスでは「安くたくさん作って高く売る」ことを重視しますが、中央省庁(農水省)で、重視している視点が違うのでしょうか?
山下:
多くの官庁の指導原理は、“法律に基づく行政”です。経済分析を行って政策を立案するという“科学に基づく行政”は行われていないのが現実です。
Q3:片桐
国の補助金頼みでなく、地域独自で農業を活性化させているような地域があれば教えていただけますか。
山下:
地域の兼業農家が集まって法人を立ち上げ、集落全体で農地を守っている取り組みがあります。このメリットは、各農家が兼業先で機械の修理、経理などそれぞれ異なる知識やノウハウを身につけ、それらを持ち寄って、主業農家一人ではできない効率的な農業生産を実施できる可能性があります。
例えば、田植えの時期に備品が故障した際、農協に修理を依頼しても1カ月待ってくれと言われてしまい、田植えに間に合わなくなってしまいます。そうした際、兼業先で機械修理の技術を身につけた人がいると助かるわけですよ。同じように、化学物質の取り扱いや備品の調達などの得意分野を身につけた人がいれば、さまざまな場面で役立ちます。
加えて、高価な農業機械を個別で購入するのでなく、共有するといった合理化も可能です。法人化というハードルはありますが、一人ひとりが力を出し合って集落全体で農業を支えていくという意味で、注目したい取り組みだと思っています。
Q6:金行
最後の質問です。食料安全保障について、日本全体で大きなムーブメントが来ていると感じています。今後、より良い方向に導いていくためには、どこのボタンを押せばいいのか教えていただけますか。
山下:
重要なのは、誰のための食糧政策、農業政策かということを、私たち国民・消費者一人ひとりが考えることだと思います。食料危機が起きたときに、半年後に食料が行き渡らなくなる可能性があるような政策が妥当なのかということです。
もう1つ重要なのは、科学的な根拠に基づいた判断です。実際のデータを踏まえて、頭を働かせないといけない。
例えば、中国など海外に穀物を買い負けるといった声があります。ところが実際のデータを見ると、日本の輸入総額のうち穀物・大豆は1~1.5%しかなく、所得水準や経済力の高い日本では、価格が10倍になってもまだ買えるわけです。このように、データをきちんと押さえておけば反論できます。
世間が間違った方向に誘導されないためには、データという確かなエビデンスを分析・考察することで、より確かな戦略・打ち手を提言できる存在が重要です。御社のようなコンサルタントには、そうした役割を期待したいと思います。
齊藤:
昨今、データを活用した政策立案(EBPM)の重要が問われていますが、今回、山下先生よりお話をお伺いすることにより、データを正しく読み取り・分析することの大切さをさらに実感しました。
本日は長時間にわたり、貴重なご意見をありがとうございました。今回いただいたご意見を、今後の活動に活かしていきたいと思います。
1 農林水産省, 令和3年度食料需給表(令和4年度8月)
2 農林水産省, 米の基本指針(案)に関する主なデータ等(令和4年度8月)
3 農林水産省, 食料・農業・農村政策審議会食糧部会(令和3年11月19日)
4 USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(9 Nov 2022)
{{item.text}}

{{item.text}}