{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2050年のカーボンニュートラル達成に向け、エネルギー業界は他業界に先駆けて取り組んでいる。ただ同時に自然環境などに影響される再生可能エネルギーの導入・拡大により、市場価格のボラティリティ(変動率)による問題も生じている。加えて、多くの機器を制御するための(あらゆるモノがネットにつながる)「IoT」の活用やサイバーセキュリティ対策などの新たな整備が必要となってきている。
これらの課題解決のため、経済産業省を中心にさまざまな委員会で議論され、適宜改正がなされてきた。その論点・情報は多岐にわたるため、一元的に把握・理解し、迅速かつ適切に対処することが難しくなっている。電力・ガスの小売り自由化後は企業の新規参入を促進し、顧客にとっての選択肢を増やす試みを政府は推奨してきたが、新規参入者にとっては制度の把握はハードルにもなっている。
そこでPwCコンサルティングは2023年8月、新電力のエネット(東京・港)と共同で、制度の動向・分析を生成AI(人工知能)を使って実証した。内容は議事録の要約、複数の審議会を横断した課題の抽出、重要度評価、課題に対する想定問答のシミュレーションなどだ。このうちいくつかの課題はあるものの、人間と変わらないレベルで議事の要約や論点の抽出ができた。
生成AI活用の次のステップとして、新たなサービス設計やカーボンニュートラルにインパクトのある料金メニュー設計に適用することが考えられる。
カーボンニュートラルを実現するためには、再生エネルギーの活用だけでなく、容量や需給調整など新設された市場取引に加えて、消費者が保有する蓄電池や給湯器、電気自動車(EV)などを制御した複雑な計算が必要となることが予想される。
複雑な計算を要する料金メニューは、請求誤りによる消費者とのトラブルが懸念されるが、生成AIは料金メニューの原案生成のほか、誤請求トラブルの事前対策などが期待できる。これまで人が設計し、複雑な要件のため断念したような料金メニューでも、生成AIによる最適なプランから検証まで実施できるようになるのではないか。
上記のようなAI対応を実現するには業界特化型のデータモデルが必要になる。現在用いられているウェブなどの公開情報を用いた(1)汎用モデル(2)エネルギー業界特化モデル(3)自社固有モデル――の3つに分類される。
(3)は差異化の要素になるため当然として、制度の分析などは(2)に該当する。(2)は機密情報に該当しないものを選別したうえで、オープンなモデルとして業界別にコンソーシアムを設立し精度を高めていけば、異業種参入やサービスの多様化などが進展し、業界そのものが発展する起爆剤になるといったことを視野に入れて取り組んでいきたい。
※本稿は、日経産業新聞2024年2月14日付掲載のコラムを転載したものです。記事本文、図表は同紙掲載のものを一部修正/加工しています。
※本稿は、日本経済新聞社の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。
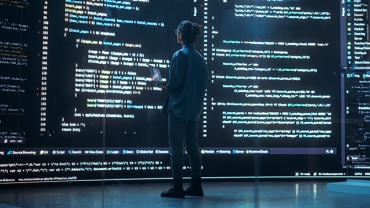
前回調査から半年が経過した今回の実態調査では、生成AIに対する認知・推進度合いが大幅に向上し、生成AIの急速な普及を実感する結果となりました。一方で人材・ノウハウ不足などの課題が見え、今後企業に求められるアクションも具体的になっています。

PwCは、先端技術を活用した事業構想の実績、AIに関する支援経験、研究機関との共同研究経験を豊富に有しております。これらを基に、生成AI市場への参入判断、生成AI利活用の導入、生成AIに関するガバナンスの構築を支援することで、デジタルディスラプション時代における企業経営の実現に貢献します。

さまざまな業界や領域においてAI/生成AIの利活用を促進する企業に対し、データプライバシーやセキュリティへ配慮したうえで信頼性・公平性を担保し、マルチステークホルダーへの説明責任を果たすAIガバナンス態勢を構築することを包括的に支援します。

私たちはテクノロジーとビジネスの専門知見で、AI活用を前提としたクライアントの成長と変革を支援します。
