
PwCコンサルティングのシンクタンク部門であるPwC Intelligenceは2025年4月、書籍『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』(ダイヤモンド社)を刊行しました。世界は米中対立と経済安全保障重視の流れのなかで大きく揺らぎ、「分断の時代」に入りつつあります。本記事は同書の執筆を担当したPwC Intelligenceメンバーのディスカッションをまとめたもので、全5回のシリーズ構成です。今回お届けするのはその第4回(前編)。PwCコンサルティングの専門家たちが議論し、「分断で変わる中国・インド・ASEANと日本企業のビジネスチャンス」について論考を深めました。前編では、中国・インド・ASEANの最新動向を検証します。

(左から)岡野 陽二、前田 良一、薗田 直孝
参加者
PwC中国 パートナー
前田 良一
PwCコンサルティング合同会社 PwC Intelligence シニアマネージャー
岡野 陽二
PwCコンサルティング合同会社 PwC Intelligence シニアエコノミスト
薗田 直孝
※法人名、役職などは対談当時のものです。
成長鈍化の中国─ただし“失速”した不動産開発投資に注目
薗田:
本日は、PwC Intelligenceの書籍『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』から、第1章「歴史と変化から考える中国市場の今後のあり方」、第2章「インドで試される日本企業のグローバルサウスへの向き合い方」、第3章「重要性を増すASEANとのつながり」の論考を踏まえて議論を深めたいと思います。なお、岡野の専門領域は中国・インド・ASEANを含むアジア、前田はPwC中国で在中国日系企業向けのコンサルティングを担当、私 薗田の専門は中国経済です。
ディスカッション前編のテーマは「世界の“分断”に伴い変化する中国・インド・ASEANの現状」です。まずは中国経済から見ていきましょう。
今の中国経済をマクロに見て、「元気がない」ことは間違いありません。特に気になるのは、想定よりも速いペースで成長が減速している点です。背景として、急激に進む人口減少と少子高齢化、根深い地域間格差、長引く不動産不況といった構造的な問題を指摘できます。
ただし、そんな状況下でも2024年の国内総生産(GDP)成長率は前年比+5%を達成し、政権が掲げた目標数値「+5%前後」をクリアしました。要因の1つは外需です。2024年12月の輸出総額は前年同月比+10.7%の3,356億米ドルにまで増え、前月の同+6.7%からさらに加速、9カ月連続のプラス成長を実現しました。翌月(2025年1月)に控えていた米国・トランプ新政権の発足に伴う関税引き上げへの警戒感から、駆け込みの輸出が急増した結果だとみられます。ただ、国内需要は不動産不況のあおりで力強さを欠き、輸入は輸出ほどには伸びませんでした。結果的に純輸出の伸びに支えられ、+5%成長を実現した格好です。
今後の見通しも確認しておきましょう。外需については、トランプ政権の対中強硬策で負の影響が及ぶと予想されます。内需の不足も引き続き懸念材料です。政府当局は消費を刺激するため、2024年から家電などの買い換え促進策を導入していますが、「カンフル剤」による景気刺激策は需要の先食いでもあり、いずれは息切れする可能性を否定できません。現地を見ている前田さんの実感はいかがですか。

PwCコンサルティング合同会社 PwC Intelligence シニアエコノミスト 薗田 直孝
前田:
不動産開発投資は「意外に活発」と言いますか、まだまだあちこちで不動産建設は進んでいるという印象です。上海などの大都市の中心部でも多くの不動産建設が進んでいる姿が見られます。日本でもかつて盛んだったハコモノ建設であったりするのかもしれませんが、林立するタワークレーンを目の当たりにし、あちこちで鳴り響く槌音を耳にすると、長いスパンではやはり不動産開発投資が中国のGDPを押し上げている面があるのだと実感します。
ただ薗田さんのご指摘のとおり、不動産不況で個人消費が低迷し、景気の下押し圧力となっていることは事実です。依然として新設され続けている巨大なタワーマンションを、一体どれだけの消費者が購入できるのでしょうか。長引く不動産不況に対し、政府も規制緩和などさまざまな対策を講じており、少しずつ回復の兆しはあるものの、「低迷を脱し回復に向かいつつある」と確信をもって言うことはできません。いずれにせよ、不動産市況については引き続き注視していく必要があると考えます。
薗田:
2024年通年の固定資産投資は前年比+3.2%で、5%に満たない水準でした。とはいえ現地で目にする実態にはまた異なる側面もあり、単純な白黒では決めつけにくい、ということなのでしょう。
参考までに、マクロではなく個別の観点で付け加えておきます。2024年通年の固定資産投資の状況をセグメント(製造業、インフラ、不動産)別に見ると、製造業投資は当局の産業振興策によるハイテク分野の伸びに支えられ、前年比+9.2%と高水準。インフラも+4.4%と底堅く着地しました。反面、不動産は-10.6%で、固定資産投資全体の足かせになっています。
「量」から「質」へ─消費性向が進化・深化し続ける中国
薗田:
内需が弱含み、経済が減速感を強める中国の足元で、個人消費のあり方が変容しつつある点は要注目です。例えば、「モノ」を起点とする物質的な消費に代わり、体験など「コト」を軸にして質を追求する新たな潮流が加速しています。前田さん、中国の消費動向についてはいかがですか。
前田:
ひと昔前は最高級品を手にすることがステータスとされ、誰もが欲しがりました。そんな爆買い的な消費を一通り経験したことで、今は懐事情も勘案しながら身の丈をわきまえ、「必要な程度だけ買えば十分」となったわけです。その結果、以前に比べて消費をダウングレードする傾向がみられます。
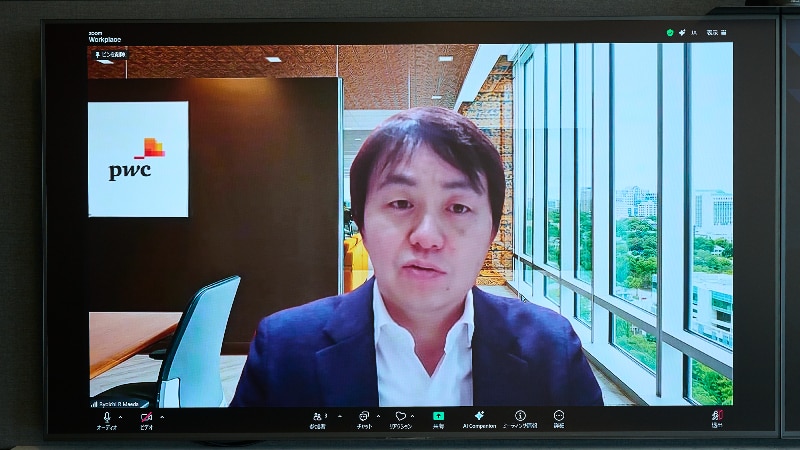
PwC中国 パートナー 前田 良一
薗田:
2001年のWTO加盟以降、中国の消費者は高い経済成長率の恩恵で裕福になり、消費をエンジョイするようになりました。良いモノを実際に手にして「高品質」に触れる──その経験を通じて審美眼が養われ、単に「高級ブランドだから」とか「高額のモノだから良いに違いない」といった動機ではモノを買わなくなりました。前田さんは「身の丈」と表現しましたが、中国の人々の消費行動についてはそうした質的な変化を十分に注視して今後の動向を追う必要がありそうです。
2000年代に成長率10%台で推移してきた中国経済は、直近の成長率こそ5%にとどまっているとはいえ、GDPの規模は10年前から倍増しています。つまり当時の10%成長と現在の5%成長は、実額ではほぼ同等なのです。しかも経済の中身をつぶさに見てみると、前田さんの指摘のように、「身の丈」に合った、成熟した消費が生まれつつあります。これはこれで、健全な経済の発展のありようと言えるでしょう。
さて、では未来にも目を向けてみましょう。引き続き前田さんに伺います。中国で注目すべき「新たな産業の息吹き」は何でしょうか。
前田:
3つ挙げられます。1つ目は電気自動車(EV)です。ご承知のとおり、中国は国策としてEVを一大産業・グローバル産業に育てようとしています。国内では補助金など政策的な後押しを受けて販売・普及が促され、ショッピングモールでEVが家電やスマートフォンと並んで売られているほど、人々の日常に浸透しています。2つ目は電動垂直離着陸機(eVTOL)です。「空飛ぶクルマ」「有人ドローン」とも呼ばれる次世代モビリティで、実際に普及するのはまだ先になるとみられますが、これを新たな産業の柱として育成するべく、投資優遇を措置した官民連携の技術開発が進んでいます。3つ目は人型ロボット(ヒューマノイドロボット)です。ロボットが走ったり踊ったりする映像をご覧になったことがある方も多いでしょう。頭脳となるAIの他、バッテリーやセンサーなどの関連技術も含めて、技術開発の動向に要注目です。
“強含み”のインド・ASEAN─分断リスクと中国失速で高まる存在感
薗田:
ここまで中国経済と産業の現状を確認してきました。岡野さんは、中国に加えてASEANやインドなど、いわゆるグローバルサウスの事情にも通じています。これらの国・地域について、どのように見ていますか。
岡野:
「日本企業がどんな国・地域に今注目しているか」という切り口でお話しします。参考になるのが、国際協力銀行(JBIC)と日本貿易振興機構(JETRO)が実施した日本企業へのアンケート調査です。JBICの「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告─2024年度」によると、「中期的な有望事業展開先国・地域」は、製造業・非製造業のいずれでも、トップはインドです。またJETROの「2024年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」でも、大企業の「今後の事業拡大先」としてインドは1位でした。ベトナムやインドネシアなど東南アジア諸国が両アンケートで上位にランクインした一方、中国は上位に位置するものの近年は順位を落とすか伸び悩みといったところです。
ではなぜ、インドや東南アジアなどグローバルサウスに日本企業は注目するのか。そこには3つの理由・背景があります。
第一は「地政学リスク」。米中間の亀裂をはじめ世界の分断が加速するなか、グローバルでの事業ポートフォリオとサプライチェーン強靭化の観点から、特定の陣営に与しないグローバルサウスの重要性が相対的に高まっているのです。第二は「人口」。先進国のみならず、中国でも人口減少と少子高齢化が進行しています。対して、アフリカ、東南アジア、インドなどのグローバルサウスでは人口増加が見込まれます。しかも、単にマーケットが拡大しているだけでなく、中国と同様、「モノからコトへ」のような個人消費の質的変化も見られるようになってきています。そして第三が、「中国経済の減速」です。薗田さんの説明にもあったように、中国の成長の勢いが明らかに鈍化している一方で、国際通貨基金(IMF)はインドや東南アジアの経済成長率は向こう5年間、中国を上回って推移すると予測しています。

PwCコンサルティング合同会社 PwC Intelligence シニアマネージャー 岡野 陽二
前田:
中国の企業自身も、停滞する内需からグローバルサウスのエリアに目を向け、今どんどん出て行こうとしている状況ですね。
岡野:
おっしゃるとおりです。ただ、日本企業はインドや東南アジアなどのグローバルサウスに熱い視線を注いでいますが、中国が一定の存在感を維持しているのも事実です。
先ほど言及したJETROのアンケート調査でも、大企業の「今後の事業拡大先」では、中国はインド、米国に次ぐ3位です。中国経済が鈍化し、米中対立の激化や中国リスクを警戒しながらも、実際には中国を重視する日本企業がやはり多い様子がうかがえる結果となっています。
薗田:
中国経済が減速トレンドにあるからと言って、日本企業が一気呵成にグローバルサウスに向かうかというと、必ずしもそうではない。大づかみな捉え方では中国でのビジネスに遠心力が働いているように見えても、国内に多様な側面を有している中国マーケットを、目を凝らして解像度を上げて見てみると、また違った側面が浮かび上がるというわけですね。
岡野:
ここで視点を少し変え、グローバルサウスというマーケットでの競争相手として、中国を考えてみましょう。
まず東南アジアでの中国。伸びゆく東南アジアの勢いを自国の経済成長に取り込みたいのは、中国も日本と同じです。これまで東南アジアは、マーケットとして日本企業の“金城湯池”とも言える手堅い地域でしたが、今では多くの中国企業が進出しています。代表例が、前田さんの指摘にもあったEVです。中国の新興EVメーカーの東南アジアにおける浸透ぶりには、目を見張るものがあります。この現実はしっかりと意識しておく必要があるでしょう。
インドではどうでしょうか。インドは、数1,000kmにも及ぶ長い国境線で中国と接しており、両国間には常に領有権問題がくすぶっています。それ故に中国企業が投資をしにくい状況で、これはインドと政治的なあつれきのない日本の企業にとってはアドバンテージとも言えます。
このように、「中国」という要素を交えてグローバルサウスのビジネス環境を捉える見方は、今後ますます重要になるでしょう。

