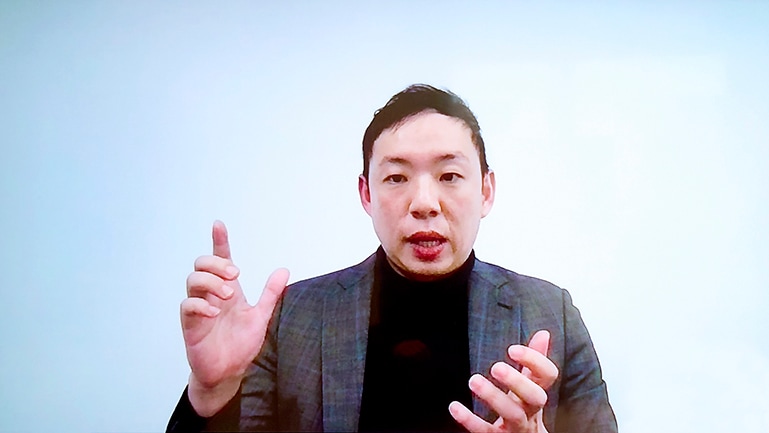{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
第2次トランプ政権(トランプ2.0)が始動し、半導体分野を含む米国の通商・産業政策は新たなフェーズに突入しました。世界最先端の半導体産業で知られる台湾は、同分野を国家戦略の中核に据え、米国への巨額投資や日本(九州)での大型プロジェクトを含む対外進出と台湾での拠点維持を同時に推進しています。半導体製造で一歩後れをとる日本も、北海道と九州に新たな生産拠点を構築しました。そこで今回、台湾の半導体戦略の最新動向と、日本企業が目指すべき成長戦略について、台湾政府の科学技術政策を所掌する国家科学技術委員会傘下のシンクタンク「科学技術、民主と社会研究センター(DSET)」CEOの 張智程氏をお迎えし、PwCの専門家2名とともに議論しました。
(本文中敬称略)
(なお、本記事は2025日3月下旬時点の情報に基づき作成しています。)
(左から)吉田 知史、内村 公彦、張 智程氏
登壇者
張 智程 氏
科学技術、民主と社会研究センター
(Research Institute for Democracy, Society, and Emerging Technology:DSET)
CEO兼経済安全保障研究グループ長/博士(法学)
内村 公彦
PwCコンサルティング合同会社 パートナー/執行役員
モデレーター
吉田 知史
PwC Japan合同会社 マネージャー/博士(政治学)
吉田:
米中の対立が第1次トランプ政権(トランプ1.0)で本格化した結果、あらゆる経済活動を安全保障の文脈から捉えなおすことが進み、「経済安全保障の時代」が到来しました。経済安全保障には「守り」と「攻め」の両面があります。トランプ1.0では特に「守り」の戦略として中国とのサプライチェーンの分断(デカップリング)を志向し、米国だけでなく友好パートナーに対しても、中国との経済関係の見直しを求めてきたと思います。その中で台湾の半導体産業が非常に注目を集めてきたわけですが、台湾はどのように対応してきたのでしょうか。
張:
台湾の対応は、大きく2つに分けて整理できます。まず、2022年に「国家安全法」を改正し、「国家核心重要技術」の概念を明確に定義しました。国家安全法にはそれまで、どんな技術が台湾の安全にとって重要なのかを見極めるプロセスが欠けており、その技術をどう保護するかの枠組みもなかったのです。これを改めました。
次に、同じく2022年に「両岸人民関係条例」を改正しました。同条例には、台湾企業が中国に対し技術移転や投資を行う際の審査メカニズムを定めたものが含まれます。この改正により、特に半導体などの戦略技術の移転に関して、台湾の高度人材の中国による引き抜きや、技術獲得を目的とする拠点設置について台湾の当局が積極的に介入し、取り締まりを強化できるようになりました。
DSET CEO兼経済安全保障研究グループ長/博士(法学) 張 智程氏
吉田:
一方、「攻め」の経済安全保障では、第1次トランプ政権は産業政策の再構築に取り組み、特に最先端の半導体製造や研究開発を米国に回帰させる方針を掲げました。バイデン政権もこれを引き継ぎ、「CHIPSおよび科学法(CHIPSプラス法)」に基づく補助金により、半導体企業の対米投資拡大を促しました。台湾に変化はありましたか。
張:
かなり大きな変化がありました。米国に続き、日本や欧州連合(EU)特にドイツなどが半導体製造の戦略的重要性を強く意識し始め、自国・自地域へ台湾の半導体企業を誘致しようとし始めました。台湾の半導体産業が世界的に注目されるようになったのです。
台湾自身も半導体を単なる商業製品ではなく、国家安全保障や経済安全保障上、極めて重要な役割を担う戦略物資として再定義しました。「シリコンシールド」(シリコンの盾)という言葉のとおり、半導体産業の存在が台湾の戦略的重要性をさらに高め、特に友好国でその価値が再認識されるようになりました。台湾が持つ最先端の半導体技術を、友好国とどのように共有すれば台湾の安全保障・経済安全保障上のメリットになるか──これを見極めることが台湾にとってますます重要になるでしょう。
吉田:
第2次トランプ政権(トランプ2.0)は、CHIPSプラス法のような補助金を使った産業誘致に対する否定的な見解を繰り返し示し、実際に関税を含むさまざまな手段を用いて、米国の台湾への要求を強めています。
張:
2025年3月、台湾企業のCEOがトランプ大統領とともに新たな投資プロジェクトを発表しました。その内容は、米国での生産能力を大幅に拡大するため、1,000億米ドルの追加投資を行い、新たに3つのウエハー工場、2つの先進パッケージング工場、研究開発センターを設立するというものです。
この投資は、台湾にとって新たな展開の第一歩です。台湾は、米国との相互依存関係を固めるとともに、経済的合理性やコストパフォーマンスを考慮しながら、台湾の安全保障や現状の国際的地位を守る最適なバランスを模索する必要があります。
吉田:
台湾はこれまで中国に対して、最新世代よりも1世代古い技術についてのみ対外投資を許可するN-1政策を採用してきました。この政策は今後、米国を含む全世界に適用されるのでしょうか。
張:
N-1政策は「両岸人民関係条例」にのみ規定された条項であり、もっぱら対中投資に係る規制として運用されてきました。一方、これまで中国以外の国に対しては、いわば「戦略的曖昧性」のアプローチを採用し、経済部(日本の経済産業省に相当)と企業による暗黙の了解の下で規制を行ってきました。例えば、台湾企業が日本に進出するには公的な許可が必要ですが、N-1政策が適用されるかどうかは明示されていません。
しかし経済安全保障の視点から、今後は他国にも適用される可能性があります。2025年3月、立法院(国会に相当)での質疑の中で、国家発展委員会主任委員(経済財政政策担当大臣に相当)である劉鏡清氏は、N-1政策の適用範囲が中国に限定されず、米国への投資にも適用されると発言しました。台湾の科学技術戦略に政策的な変化が生じつつあることは確かです。
吉田:
そもそも極めて高い経済効率を誇る台湾の半導体企業が対米投資を行うことには、生産性が低下するなどのリスク──たとえそれが短期的なものであっても──を伴うはずです。そうしたリスクがありながらも対米投資を進める理由は何なのでしょうか。
張:
台湾の半導体産業と米国のシリコンバレーとが緊密な協力関係を築けば、新たなサプライチェーンが形成されることを期待できるからです。AIやクラウドコンピューティング、量子コンピューティングなど人類文明に変化を及ぼすあらゆるエマージングテクノロジーに関しては、やはり米国企業がリードしています。台湾企業による対米投資の拡大は、こうしたテックプラットフォームやAI企業といったアプリケーション側との、より緊密的な協力関係の構築につながります。
一方で、半導体製造に関わる台湾におけるエコシステムを守ることが米国を始めとする諸外国の利益につながるのだと説得し続けています。ご指摘のとおり、世界がグローバル化する流れの中でさまざまなステークホルダーの意思決定が作用した結果、台湾は先端半導体の製造にとって最も効率的で、経済的合理性があり、しかも最もサステナブルな拠点になりました。半導体の製造には、数百~数千のサプライヤー、優れた専門人材、さらに経験に裏付けられた高度なエコシステムの構築・維持が不可欠です。そんなシステムを短期間に全て別の場所に移すことはまずできません。
もし仮に、台湾の半導体産業が世界的な優位性を失えば、代わって中国が主導権を握る可能性が高まります。先ほど言及したAIやクラウドコンピューティング、量子コンピューティングなどの次世代技術は、米中覇権争いの鍵を握る要素です。台湾企業が提供してきたこうした最先端のチップ供給が不安定化すれば、それは台湾にとっても、西側諸国にとっても、望ましくない未来のはずです。
ですから、台湾にとって最善の選択肢は、米国での生産活動にも最大限努力し、生産効率などの経済合理性を高めながら事業を展開していくことなのです。
吉田:
ファウンドリーにとってもアプリケーション側との協力というのが非常に重要であるというご指摘は、日本企業にとっても言えるではないでしょうか。外部環境が複雑化する中で、日本の半導体産業の課題は何でしょうか。
内村:
半導体のチップセットは10年単位でスタンダードライゼーション(標準化)の波と、カスタマイゼーションの波があります。本年のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)では、ヒューマノイド型ロボットがその辺を歩いて介護しているような世界が実際訪れるだろうという講演がなされていました。先端あるいは次世代の半導体は、カスタマイゼーションの世界に入っていると思います。
日本では、国産半導体メーカーが北海道にチップセット工場を建設し、専用多品種のものをタイムリーに供給する戦略で、カスタマイゼーションの波に耐えていこうとしています。この場合のアプリケーション先として、例えば、自動車産業は特に有力な市場の1つです。自動車は近い将来、SDV(Software Defined Vehicle)が主流になると考えられ、そこでは極めて高度な半導体技術が不可欠です。日本の強みである自動車産業を軸に市場を開拓するのは有効な戦略です。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー/執行役員 内村 公彦
一方、九州では台湾のファウンドリー企業と共同で受託生産拠点を整備していますが、こちらは最先端半導体を製造しているわけではなく、ドローンのような標準化されたアプリケーション市場がターゲットです。現在、ドローン産業は中国企業が寡占していますが、日本・台湾・米国が合意して連携すれば、中国製以外のドローン市場を形成できる可能性があります。
吉田:
ドローンには台湾も注力しています。昨年9月には経済部がリーダーシップをとって「台湾卓越無人機海外商機連盟」という企業連携組織を新設しました。台湾の狙いは何でしょうか。
張:
海に囲まれている台湾は、有事に海上封鎖されると物資調達が困難になります。そのため、ドローン生産のサプライチェーンを台湾内に確保することが急務なのです。とはいえ現在は中国の商用ドローンが市場を席巻しており、台湾の中小企業が製造してもコストが3〜10倍かかるため競争が難しい状況です。そこで台湾では、政府主導でプラットフォームを整備し、各企業が自社の技術でドローン開発に参入できる環境を整えています。
吉田:
九州の生産拠点は、どのように位置付けられていますか。
張:
日本には、ドローンの最終製品化に関わる技術を持つ中小企業が多数あります。九州の生産拠点を活用してそれらの技術を結集すれば、台湾・日本の双方にとって大きな戦略的メリットが生まれます。農業用あるいは災害対応用などのドローンに関して台日研究開発コンソーシアムを九州の大学などに設けることも一つのアイデアです。
内村:
かつて日米半導体協定の交渉代表を務めた牧本次生氏(2025年5月よりPwCコンサルティング合同会社の顧問に就任)も「日本はアプリケーション市場で主導権を握ることが重要」である旨を指摘しています。特にロボット産業を日本のコアコンピタンスにする国家戦略を持つべきだという考え方です。
それ以外ではヘルスケア領域も有望ですね。入口としてローカルな課題の解決というのは筋が良いと思います。地方ではヘルスケアの課題が深刻なので、それを解決するための研究開発を大学などと連携して深化させ、その成果を日本各地に展開すれば、九州の生産拠点が量産化を支える役割を果たせるでしょう。
日本の研究開発の強みを生かし、アプリケーション市場を結び付け、規模は追わずに利益率の高い市場を狙う戦略も必要です。小規模でもまずサービスを市場に投入し、国として必ず利益が出せる状態を創出すること。その後に重要なのは、台湾のEMS企業などと連携してスケールアップさせて米国市場へ持ち込むことだと思います。このような協力で、日台がWin-Winの関係を築くことが重要です。
張:
世界的にサプライチェーンのデカップリングが進む中、日本との連携を強化し、中国に過度に依存しない供給網を構築することは、台湾の安全保障および経済安全保障にとって極めて有益です。
吉田:
最終財の研究開発については日本が、量産化や効率性の向上については台湾が強みを持っており、日台はそれぞれの比較優位が補完性のある関係なのだと思います。今後、これを重要なアジェンダとして深めていきたいと思います。本日はありがとうございました。
PwC Japan合同会社 マネージャー/博士(政治学) 吉田 知史
{{item.text}}

{{item.text}}