
足元の中国経済はゼロコロナ政策解除後に期待された「リベンジ消費」の勢いが持続せず、不動産市場の低迷も続いている1。さらには欧米景気の先行き不透明感が払拭されず外需を取り巻く環境も厳しく、内憂外患の厳しい状況にある。中国国内では若年層を中心に雇用不安も払拭されないなど多くの課題を抱えるなか、第3期目がスタートした習近平政権が目指す「2023年のGDP成長率5%前後」の達成も危ぶまれている。
政府当局は、大規模な財政出動を伴う景気刺激策を通じて目先の経済の腰折れを回避するのではなく、「国家安全」を最優先課題としている。すなわち、貧富の差の是正を目指す「共同富裕」との理念の下、長期的な観点から経済成長を維持・安定化させるため、国内各産業に残存する前近代的な規制の緩和や、不均衡や不平等の是正といった構造問題への取り組みを模索する姿勢がうかがえる。ただし、共産党政権による国家統治の正当性を人民に指し示すためには経済成長の実現が求められているなか、大規模な景気刺激策を打たずして経済をいかに回復させるのか、次世代につながる新しい産業を育成しつつ安定的かつ質の高い経済成長は維持できるのかといった課題に直面している。
こうしたなか、中国国内では、政府当局による政策の恩恵が国有企業に集中する「国進民退」の傾向が2022年から顕在化しており、これが中国経済の今後の成長や発展に与える影響が注目されている。以下では、中国国内の国有および民営企業を取り巻く歴史・経緯のほか、足元の経済指標からうかがえる動向を踏まえつつ、「国進民退」の傾向が中国経済に与える影響や今後の見通しについて筆者の見解を述べていく。
国有企業および民営企業を取り巻くこれまでの経緯――揺れ動く「国進民退」の動き
「国進民退」は中国共産党や政府当局の方針として正式に打ち出されているものではなく、あくまで中国の経済や各産業において国有企業が民営企業より優遇されているとうかがえる現象や状況を指すものである。以下で「国進民退」について論じるに先立ち、中国における国有企業および民営企業を取り巻く歴史・経緯を振り返っておこう。
社会主義を掲げる中国において、国有企業は中国経済の根幹と位置付けられており、エネルギーや素材、通信や金融といった主要産業セクターを独占している。国有企業は政府当局の政策実現のための重要な担い手であり、雇用を創出し社会の安定に寄与する存在として位置付けられている。歴史を振り返ると、かつて中国の都市住民は国有企業への就業とともに、住宅や学校、病院、商店など全ての社会生活インフラを有する「単位」に身を置き、“生老病死(ゆりかごから墓場まで)”制度の下で従業員とその家族の生活が支えられていた。また、国有企業の経営者は共産党の高級幹部であり、共産党および政府当局に対して高い忠誠心を持っている。中央および地方政府は各種政策や金融面での手厚いサポートにより国有企業のプレゼンスを高めるとともに、国有企業を通じて経済活動をコントロールする構図が中国には根深く定着していると言える。
上述のとおり、国有企業は雇用確保や従業員の福利厚生といった社会保障機能の役割を担ってきたほか、長年の計画経済体制下、国有企業には非効率な経営体制が残存していた。こうしたなか、1990年代に鄧小平氏により社会主義市場経済が提唱され市場経済化が推進された。
1 中国不動産市場の足元の動向については、PwC Intelligenceのレポート「「共同富裕」のジレンマに直面する中国不動産市場-構造問題に阻まれ低迷が続く住宅需要」を参照のこと。
続きはPDF版をご覧ください。
レポート全文(図版あり)はこちら
PwC Intelligence
――統合知を提供するシンクタンク
PwC Intelligenceはビジネス環境の短期、そして中長期変化を捉え、クライアント企業が未来を見通すための羅針盤となるシンクタンクです。
PwC米国の「PwC Intelligence」をはじめ、PwCグローバルネットワークにおける他の情報機関・組織と連携しながら、日本国内において知の統合化を推進しています。

本ページに関するお問い合わせ
関連情報


地政学リスクマネジメント対応支援
米国と中国の間での貿易摩擦や英国のEU離脱を巡る混乱など、地政学リスクのレベルが高まっています。日本企業にも、リスクマネジメントに地政学の視点が必要です。事業に対する影響の評価、リスクの定量化、シナリオ予測などの手法を用いて、地政学リスクによる損失の軽減や未然防止に向けた効果的・効率的な対策立案と実行を支援します。

サステナビリティ情報開示支援
サステナビリティの知見とサステナビリティに関する各国法規制や国際ガイドラインを熟知したメンバーが企業の情報開示を支援します。
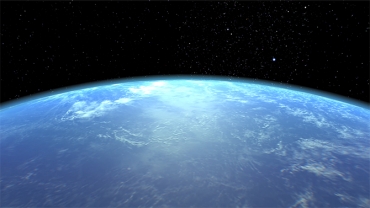
宇宙・空間産業推進室
PwCコンサルティングは、気候変動など地球規模の課題解決に向けて、「宇宙・空間」をリアルとデジタルの双方から俯瞰した視点で捉えていくことで、陸・海・空、そして宇宙における分野横断的な場づくりや関連産業の推進、技術開発、事業活動を支援しています。
