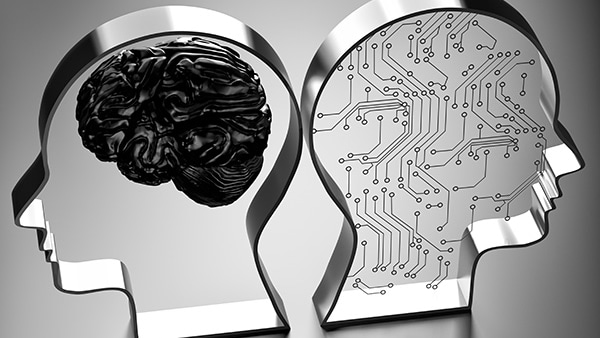{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
このたび「監査の変革」の更新版(2024年版)を発刊しました。生成AIをはじめとしたAI技術の発展や、監査業務へのテクノロジー導入経験の蓄積によりAIに関する知識・理解が深まったため、内容を更新しています。
本稿ではAI(人工知能)の監査への適用可能性ならびに、被監査会社および監査人にもたらす効果について考察する。
AIはニューラルネットワークなどの機械学習1や質問応答システムなどの自然言語処理2の発展に伴って、近年注目を浴びているが、監査においては、まだ実用化に至っているケースが少ない。一方で、監査現場の作業量は年々増加しており、生産性の向上が求められ、また、監査のステークホルダーからの期待に応えるための品質向上についても課題がある。さらには、2020年において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により、各企業ではリモートワークの導入が推進され、業務の自動化、紙書類の廃止によるデジタル化が進むことが推測される。これらの課題に監査手続のAI化・デジタル化は有効な手段となり得ることから、監査法人では日々研究開発を進めている。
監査業務におけるAIの適用を進めるにつれ、AI技術自体の高度化や、AIに関する知識・理解の深度化、監査業務への導入経験の蓄積等により、2018年に刊行した「監査の変革」の情報を更新することが有用であるため、今回2021年版を発刊するに至った。
1 機械学習(Machine Learning)とは、AIの領域の一つであり、データに潜むパターン(法則性やルール)をコンピューターに自動的に発見させる技術である。このパターンによって判断や予測を行うことができる。
2 自然言語処理(Natural Language Processing)とは、人間が普段用いている自然言語をコンピューターに処理させる技術である。翻訳、検索エンジン、音声認識、OCRなど、すでに幅広い分野に自然言語処理が応用されている。
図表1:監査業務変革の段階的進歩と働き方の変化
前段で述べたとおり、監査業務における課題に対し、AIの適用は有効な手段となり得るが、監査手続で用いるAIの学習のためには、大量の標準化されたデータを用意する必要がある。しかしながら、従来監査業務において、AIに投入できるようなデータの標準化は行われていない。その理由は、被監査会社によって会計システムおよび、注文書、請求書といった会計処理に必要な証憑が異なり、また監査人側においても被監査会社のビジネスが異なることで監査調書のフォーマットが被監査会社ごとに異なる、といった状況のためである。現状ではAIに学習させるためのデータの前処理工程が膨大となってしまう。
将来、AIを用いた監査を行うためには、①業務プロセスおよびデータの標準化、②監査手続のデジタル化、③AIの導入、という3つのステップを踏まなければならない。①の手始めとして、専門的な知識を必要としない監査手続を集約的に行うセンターを設置し、運営の過程で業務プロセスを統一する、もしくは共通のデータフォーマットに変換することで使用できる分析ツールを監査法人内で普及させ、各被監査会社のデータを共通のフォーマットに統一する、といった方法によって、標準化を進めていくことになる。
次章において具体的な監査手続の変化について説明する。
前章で示したAI導入前のステップを経て、現在およびAI化した場合の将来の監査手続例や、被監査会社と監査人にもたらす品質向上もしくは時間削減効果、監査手続におけるAI化の代替可能割合、そして将来の監査手続が実現すると見込まれる時期を図表2に示した。
各監査手続をAI 化させるためには、前章で説明した標準化やAIの基盤となる監査プラットフォームの開発等は不可欠であるため、AI 化を実現させる環境についても示した。
前項で主要な監査手続のAI化について触れたが、ここでは勘定科目ごとの一連の監査手続がAI化によってどのように変わるかを述べる。
監査計画において識別・評価する重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体レベルとアサーションレベルの2つに分類されるが、後者のアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクは概ね各勘定科目に紐づくリスクのことであり、監査手続の大部分の時間を占めているのが各勘定科目に関するリスク対応手続である。勘定科目ごとに業務フローや監査上のリスク、計上証憑も異なることから、監査人(監査チーム)は勘定科目ごとに担当者を決定し、監査手続を実施している(売上と売掛金のように密接に関連する勘定科目同士も存在し、その場合は同一の担当者が行うこともある)。現預金勘定を題材とした勘定科目ごとの監査手続例は図表3のとおりである。被監査会社から各勘定科目の明細を入手し、それらに対し各監査手続を実施することで、監査証拠を入手する。現状このような一連の手続は、資料の依頼段階から全て会計士が実施するか、もしくは手続の一部について専門的な判断が不要な作業を会計士以外のスタッフが担当し、必要に応じて作業内容を会計士がレビューするが、割合は高くない。
AI化が進んだ事例は図表4である。被監査会社への依頼資料は、監査プラットフォームに集約され、被監査会社から資料がアップロードされると、紙資料についてはAIがOCR5で資料をデジタル化し、デジタル化された全てのデータを標準化した後、AI分析ツール等に投入する。現預金勘定では主に金融機関への確認手続が重要となるが、それらの情報も金融機関から自動取得し、回答結果を照合する。AI分析ツール等により異常な結果が出力された場合、必要に応じて被監査会社に質問し、その回答内容を反映させる。以上により入手した監査証拠は自動で監査調書に文書化され、監査人がレビューを行う。
5 OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)とは、手書きの文字や印刷された文字を画像データとして読み取り、文字を認識してテキストデータへ変換する技術である。テキストデータ化することでコンピューターが文字情報を扱いやすくなる。
前項で説明した勘定科目ごとの監査手続のAI化が、各勘定科目でどの程度進むかを表したものが図表5である。
「AI導入の阻害要因」として、「経営者の恣意性の介入」、「物理的な現物の存在」、「被監査会社のビジネス形態による影響度合」といった3つの要因を設定した。「経営者の恣意性の介入」は、会計上の見積り等、経営者の主観性や恣意性を反映する余地がある勘定科目かどうか、「物理的な現物の存在」は、商品・製品や工場の建物、機械装置といった監査上検証が必要な現物が存在するかどうか、「被監査会社のビジネス形態による影響度合」は、売上高や棚卸資産等、被監査会社のビジネス形態によって、監査上検討すべきリスクの所在が異なる可能性が高いかどうかを示したものである。これら「AI導入の阻害要因」の影響が大きいほど、AI導入の難易度が高くなり、「AIの代替割合」が下がることになる。
前述で事例とした現預金勘定は、現物は存在するものの、経営者の主観性や恣意性は介入しづらく、ビジネス形態の影響も受けにくいため、「AIの代替割合」は高程度になると予想される。一方で、棚卸資産は被監査会社のビジネスによってリスクの所在が異なる、評価損の計上等経営者の恣意性が介入しやすい勘定科目である、現物が方々に存在する、などの理由から監査人の知見と経験に基づく判断が重要となるため、「AIの代替割合」は低程度と、現預金よりも低くなっている。
勘定科目によって「AIの代替割合」は異なるが、全てがAIによって完結するのではなく、AIによる監査手続で入手した監査証拠の最終的な評価は監査人が行うことになる。
次項では証憑突合を例として、監査手続へAIを適用するプロセスと導入課題について述べる。
次に、実現が比較的容易で影響が大きい証憑突合については、近年中に監査人がAI 監査ツールを導入できる可能性がある。このため、以下に具体例を述べる。
売上を検証する上での手続の一つである証憑突合は、被監査会社の規模・複雑性によって、多いときは数百万件以上に上る売上伝票を母集団として、数百件から千件以上に及ぶサンプルをテストするケースがある。サンプル数と同様に被監査会社の複雑性にもよるが、サンプル1件につき、テスト対象の抽出から、テストの実施、調書作成までにおおよそ10分~20分かかると仮定する。このようなケースでは膨大な監査時間が消費されており、AIの導入効果が高い手続である。
図表6は、証憑突合へAI監査ツールを導入した場合のフロー図である。
なお、各プロセスやテスト結果は一般的な考えを示すために簡略化している。
AI監査ツールの開発過程で、証憑データから必要な情報を抽出する精度が、証憑突合へAIを導入するにあたり主なボトルネックとなることが分かった。
まず、AI監査ツールにとってノイズとなる情報がこの精度を低下させる原因となる。例えば、証憑に含まれている社印や、被監査会社が内部統制目的で証憑へ追加した丸囲み、マーカー、チェックマーク、メモ書き、承認印などが読み取ろうとする箇所と重なっている場合、これらの情報がノイズとなる。これらを事前に除去できれば、変換精度を著しく改善できると予想される。
また、証憑書類の様式のバリエーションが多いと精度低下の要因となる。例えば、売上プロセスでは注文書の様式が得意先ごとに異なるため、この影響を受けやすい。もし、手掛かりとしてテスト対象の座標情報を使って読み取る場合、各様式をAI監査ツールへ記憶させる必要がある。
座標情報以外の手掛かりを使ってデータを抽出することもできるが、事前設定を行わずに全ての証憑書類の様式へ対応するには、データ収集とさらなる研究開発が必要である。
最後の課題が、会計システムから出力したデータと証憑データとを紐づけるためのキーの抽出である。キーの抽出が失敗すれば、その証憑にかかる証憑突合が全て無効となるため、100%の精度が求められる。
ある会社では、売上金額、数量等が記載された特定の証憑(A)にキーが含まれておらず、別の証憑(B)を経由しなければ取引と紐づけられなかった。この場合、証憑(A)の紐づけ処理を証憑(B)の紐づけ後に行う必要がある。
他の会社では、キーを証憑へ直接書き込んでいた。この場合、キーとなる情報の位置を自動検出し、手書き文字を正確に読み取る必要がある。
以上より、図表7のように、1. ユーザーにとって必要な情報がAI監査ツールにはノイズと映ること、2. 証憑書類の様式が会社ごとに多様であること、3. キーとなる情報を正確に抽出するための工夫が必要であることから、監査用証憑データの形式変換の精度がボトルネックとなっている。
このような課題を克服し、証憑データの変換作業をAI監査ツールに学習させて自動化するには、マニュアル作業によって学習データを用意する必要が生じる。このため、AI監査ツールが十分な精度に達するまでは、監査人がツールのテスト結果をチェックして効率的に精度を改善することが求められる。
しかし、ツールの精度が100%に近づけば、監査人はAI監査ツールに依拠することができる。被監査会社が証憑を全て電子ファイルで保存している場合など、状況によっては全取引をAI 監査ツールでテストすることで、内部統制に依拠せずとも必要な保証水準を得られるようになると予想される。この場合、監査人はAI監査ツールが検出した項目の評価と判断を行い、ツールの調整や検出項目のフォローについて被監査会社とコミュニケーションすることになる。
将来的に、売上テストのような証憑突合では、AI監査ツールによる自動化によって、人手に依存しなくても正確なテスト結果が得られるようになる。
加えて、被監査会社が古い資料や誤ったファイルなどをアップロードしてしまった場合、即時に提示されるテスト結果によってエラー結果に気づくことができ、監査人の介在なしに適切な証憑へ訂正することができる。
このように、AI監査ツールの開発過程で特定された課題を解決できれば、AI監査ツールによる証憑突合自動化は監査の変革へ大きな可能性をもたらすと考えられる。
コンピューターやインターネットの進化により、2010年代から注目されたビッグデータは、今では一般的な用語としてなじんでおり、またビッグデータの登場に関連してディープラーニングが台頭し、AIブームに火が付いた。ビッグデータを用いた分析は経営の主流で、ビッグデータをAIに投入してビジネスチャンスを得る、という概念も当たり前になっている。企業にとって自社のビジネスに関連するデータをより多く抱えることは重要で、それに加えて今後は新型コロナウイルス感染症等の影響により、これまでデジタルの活用を検討しなかった企業もビジネスモデルを改めると推測され、デジタル社会はより一層促進することが見込まれる。
現状の監査現場においても、増大した被監査会社のデータ加工・分析処理には時間がかかっており、監査人の労働時間が増加する一因になっていたが、このような膨大な量のデータを容易に処理可能な加工・分析ツールも発展してきており、監査現場への導入が推進されている。しかしながら、データの標準化という課題を抱え、AIの導入は難航している。それに加えてそもそものデータの正確性や網羅性、正当性といった観点での、データ自体の信頼性を検証するツールはまだ出てきていない。
上述のとおり、企業が扱うデータの量も重要性も年々増しているが、将来、ビジネスの根底および、適切な財務報告を支えるデータの信頼性に疑義が生じれば、企業自身に重大な影響を及ぼすことになり、データの信頼性の担保はコーポレートガバナンスの観点からも重要である。企業のさまざまなデータの信頼性を客観的に保証することは、現在の技術では難しいものの、将来はその領域にもAI が活用されると見込まれる。関連して、監査人の業務も財務諸表監査など従来の保証業務のあり方にとどまらず、リアルタイムでのリスク対応手続および、被監査会社とのコミュニケーション、その先の未来予測を利用した監査といった領域に活躍の幅を広げ、監査人は会計監査のノウハウとAIを活用し、データやプロセスの信頼性に関する業務を幅広く担うことになるだろう。
財務報告の領域を超えて、企業を形成するさまざまなデータの保証はやがて企業全体の保証業務となり、それらを担う監査人を支えるものは、発展したAIと自らの知見・経験である。
PwCあらた有限責任監査法人(以下、「PwCあらた」)は、PwCの世界152カ国にまたがるグローバルネットワークとも連携し、テクノロジーの活用をより深化させ、高品質かつ効率的な監査の実現を目指している。また、人間と機械の最適な分業による、次世代の会計監査の在り方を追究している。
Genial Technologyはクラウドコンピューティングと人工知能によって、会計データクレンジングおよび監査人・被監査会社間の監査証憑の授受を含む、監査手続を自動化するソフトウエアの提供を目的とした会社である。
PwCあらたとGenial Technologyの目的は補完的であり、この種類の共同研究活動においては優れた専門性と研究分野の組み合わせとなる。例えば、PwCあらたが会計監査における幅広い知見を提供し、Genial Technologyはデータクレンジング、データ分析およびAIモデル開発についての知見を提供する。
PwCあらたは、市場をリードするプロフェッショナルのスキル、堅実な監査アプローチ、人工知能(AI)をはじめとするテクノロジーを融合した新時代の監査を通じて、デジタル社会に信頼を築くプロフェッショナルファームを目指します。
{{item.text}}

{{item.text}}