
買収した法人がグループ通算加入時期の特例の適用中に合併した場合の取扱い
2023-11-17
Question.
当社(P・通算親法人・3月決算)と子会社(S1・通算子法人・3月決算)は、グループ通算制度を適用して法人税申告を行っています(以下「通算グループP」といいます。)。
今回X1年10月10日においてS1が株式買収を実行し、買収対象会社(S2・3月決算)の発行済株式の全てを取得したため、S2は当社と完全支配関係を有することになりました。なお、S2は通算グループPとの共同事業要件を充足しておらず、通算グループへの加入においては時価評価・繰越欠損金の切捨てが適用されることが想定されています。
当社としては、株式買収が期中であったことから、決算申告にかかる実務作業負担に配慮して、S2について翌期首(X2年4月1日)を加入日とする加入時期の特例を適用しました。その後、買収後におけるグループ経営効率化の観点から検討を進めたところ、S1がS2を吸収合併するのがよいと判断し、X2年2月1日を合併期日として合併を実行しました。
今回のケースにおいて、S2はグループ通算制度の適用に当たってどのような取扱いとなるでしょうか。また、S2は通算グループPへ加入や離脱することとなり、時価評価や投資簿価修正の適用がされることとなるのでしょうか。

Answer.
S2は通算グループPに加入・離脱することはありません。したがって、S2にグループ通算制度における加入時の時価評価等が適用されることはなく、また株主であるS1において投資簿価修正等の適用もありません。
1. 株式買収が行われた場合の通算グループへの加入時期について
(1)加入時期の原則的取扱い
内国法人(通算除外法人1を除く)が通算親法人との間に通算親法人による完全支配関係(通算除外法人及び外国法人が介在する場合を除く、以下同様)を有することとなった場合には、原則として、完全支配関係を有することとなった日において通算制度の承認があったものとみなされ、通算制度の承認は、完全支配関係を有することとなった日(加入日)から効力が生じます(法法64の9⑪)。
また、法人税法上のみなし事業年度として、内国法人が通算グループに加入する場合には、内国法人の事業年度は加入日の前日に終了し、次の事業年度は加入日から開始するものとされています(法法14④一)。なお、通算子法人で通算親法人の事業年度終了の時に通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人の事業年度はその終了の日に終了するものとされており(法法14③)、事業年度の中途により合併により解散した場合は合併の日の前日に事業年度が終了することとされています(法法14①二)。
したがって、今回のケースにおいて、もしS2が通算グループへの加入について原則的取扱いを受ける場合は、次の図表2のようになります。

(2)加入時期の特例
会計期間の中途において通算親法人による完全支配関係を有することとなった場合(原則的取扱いを受ける場合に期中加入となるケース)には、加入時期の特例を受ける事ができます。
加入時期の特例とは、通算グループへの加入時期を完全支配関係発生日(原則加入日)ではなく、加入する法人の会計期間(通常の事業年度)又は月次決算期間の末日の翌日とするものです。具体的には、加入する内国法人の原則加入日の前日の属する事業年度を完全支配関係発生日の前日で終了させずに会計期間又は月次決算期間の末日に終了するものとし(法法14⑧一)、その翌日において通算制度の承認があったものとみなして、同日から承認の効力を生じさせるというものです(法法64の9⑪括弧書)。
加入時期の特例を受けるためには、この特例の適用がないものとした場合に生ずることとなる原則加入日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限となる日までに、通算親法人が自らの加入時期の特例を受ける旨等を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(法法14⑧、法規8の3の3)。この届出書には、通算親法人や加入する法人の基本事項の他、原則加入日(完全支配関係発生日)、原則加入日の前日の属する特例決算期間(会計期間又は月次決算期間)、通算子法人最初通算事業年度などを記載します。
今回のケースにおいては、届出書には原則加入日(完全支配関係発生日)はX1年10月10日、原則加入日の前日の属する特例決算期間はX1年4月1日からX2年3月31日、通算子法人最初通算事業年度はX2年4月1日からX3年3月31日と記載し、これをX1年12月9日までに提出したということになります。この届出書提出時点においては、図表3のような取扱いとなることが想定されています。なお、法律における用語の定義上、完全支配関係発生日を原則加入日と記載していますが、今回のケースにおけるS2の通算グループPへの加入日は、X2年4月1日と予定されることになります。

(3)特例決算期間中に完全支配関係を有しなくなった場合の取扱い
加入する法人が上記(2)の加入時期の特例を適用している場合において、原則加入日(完全支配関係発生日)からその日の前日の属する会計期間又は月次決算期間の末日までの間に通算親法人による完全支配関係を有しないこととなるときにおいても、その法人の事業年度は原則加入日の前日に終了せず(法法14⑧二)、その法人が通算親法人との間に完全支配関係を有することとなった日において通算制度の承認の効力が生じないことは変わりません(法法64の9⑪括弧書)。つまり、加入時期の特例決算期間中に完全支配関係を有しなくなった場合、通算制度の承認の効力が生じることはありませんので、通算グループに加入することはありません(通算グループに加入しませんので、離脱することもありません。)。そのため、グループ通算制度の適用がない通常どおりの単体申告を行うこととなります。
特例決算期間中に完全支配関係を有しなくなる典型的な例は、特例決算期間中に通算親法人がその法人の株式の全部又は一部を通算グループ外に売却する場合が考えられますが、今回のケースのように吸収合併により消滅することが原因で完全支配関係を有しなくなるケースについてはどのように取り扱うかについて検討します。
今回のケースでは、S2は特例決算期間としてX1年4月1日からX2年3月31日を届け出たものの、X2年2月1日に合併を行うことから最終事業年度(決算期間)は自動的にX1年4月1日からX2年1月31日と変更されることになります。そのため一見すると、特例決算期間も合併により自動的に同様に変更され、その末日(X2年1月31日)においてはまだ完全支配関係を有していることからその翌日(X2年2月1日)において通算制度の承認の効力が発生する、つまり一旦通算グループに加入した上で合併が行われるのではないかという誤解が生じやすいケースと言えます。法律の条文(法法14⑧一)においては、「特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号に同じ)の末日まで継続して…」と記載されていることから、合併により最終事業年度が変更されたとしても、届出書に記載された期間に変更はなく、その末日(X2年3月31日)まで完全支配関係継続しなかったことから、通算グループに加入も離脱もすることのないまま、グループ通算制度の適用がない通常どおりの単体申告を行うという取扱い(図表4参照)となります。

上記の取扱いは、届出書(完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類)の記載要領の留意事項において示されています2。なお、通算親法人の会計期間に合わせて会計期間の末日を前倒しする会計期間の変更をした場合は、合併の場合とは異なり特例決算期間の末日は自動的に変更後の会計期間の末日となり、通算子法人となる法人には変更後の会計期間の末日の翌日に通算承認の効力が生じることも示されていますので注意が必要です。
2. 考察
今回のケースにおいては、S2は通算グループPへの加入において共同事業要件を充足しない時価評価対象法人であることから、原則どおりにS2を通算グループPに加入させた場合にはS2の加入直前事業年度において時価評価課税が生じることとなります。しかしながら、S2が加入時期の特例を適用しつつ、特例決算期間中に通算子法人であるS1に合併したことで通算グループPへの加入が生じないこととなるため、S2に対して時価評価課税は生じないこととなりました。なお、S1とS2の合併は完全支配関係内での合併であることから適格合併であることが想定され、合併による資産の譲渡損益課税等も生じないと考えられます。
上記の取扱いを俯瞰してみますと、決算申告の実務作業や大規模なM&Aや企業再編といった近年のグループ経営の実態への配慮のための規定である加入時期の特例を利用するか否かでS2の時価評価課税の有無が分かれてしまうこともあり得ます。このため、時価評価対象資産(評価益)に金額的重要性がある状況等において、加入時期の特例の適用と特例決算期間中の合併を行った場合には買収時におけるプランニングの一手法として見られてしまうのではないかという懸念も生じるかと思います。しかし、あくまで合併に十分な経済合理性がある場合は、同族会社等の行為又は計算の否認(法法132)が適用されることはないと考えられます。なお、通算法人に係る行為又は計算の否認(法法132の3)は、そもそもS2は通算法人となっていないので、文理上からも適用は難しいものと考えられます。
また、仮にS2には重要な時価評価対象資産がないという前提で、買収時にのれんを含めた高い評価額で取得しているような場合、通算グループに加入した上での合併であれば一定の要件の下でS2における資産調整勘定対応金額を被合併法人調整勘定対応金額としてS1に引継ぐことで将来においてS1が通算グループから離脱する際の投資簿価修正に反映させることもできますが、今回のように加入・離脱が生じない場合にはS2株式取得の際ののれん相当額を将来の投資簿価修正に反映させることはできないので、留意が必要です。
以上のように、通算グループに加入・離脱しないことで法人にとって有利に働くケースもあれば、不利に働くケースもありますので、加入時期の特例を適用するか否かについては決算申告にかかる事務負担の観点だけではなく、その後の特例決算期間中の組織再編等の可能性を含めて慎重な検討が必要と考えられます。
1 通算取りやめから5年未経過法人、青色申告承認取消又は取りやめから5年未経過法人、投資法人、特定目的会社、普通法人以外の法人、破産手続中の法人、同一通算グループ再加入制限中の法人、法人課税信託に係る受託法人
2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/230630/index.htm
なお、国税庁HPの税務手続の案内において掲載されている届出書は、まだ新様式に差し換えられていませんのでご留意ください(2023年9月12日現在)
※本稿は、「月刊 税務QA」2023年10月号に掲載された記事を転載したものです。
※本記事は、株式会社税務研究会の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。
関連サービス

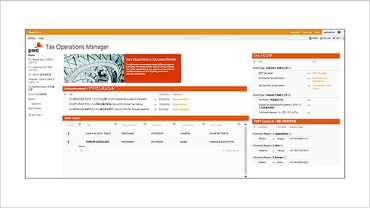
税務ガバナンス支援ツール Tax Operations Manager
Tax Operations Managerは、税務ガバナンスにおいて不可欠な各拠点の税務に関する情報収集や各拠点とのコミュニケーション支援ツールとして、情報管理プラットフォームを提供します。

M&A税務
経験豊富なM&A税務の専門家がPwCの強力なグローバルネットワークを活用して税務面からM&Aの成功を支援します。

中堅企業向けグループ通算制度導入診断
PwC税理士法人では、影響額の試算だけではなく、各企業固有の問題点を洗い出すことで課題を整理し、中堅企業におけるグループ通算制度導入のメリットを生かしたアクションプランを提案します。
