
世界的なインフレ率の高まりの中で、日本のインフレ率も徐々に高まっている。11月18日に総務省が公表した消費者物価指数(全国、10月)は総合で前年比+3.7%、生鮮除く総合(コア)で同+3.6%、生鮮・エネルギー除く総合(日銀型コアコア)で同+2.5%、食料(酒類除く)及びエネルギー除く総合(欧米型コア)で同+1.5%となった。携帯電話通信料値下げの影響が剥落した2022年4月以降、総合指数は前年比で2%を超えるようになったが、当時の物価上昇の大半を占めていたのが食料およびエネルギー価格の上昇であった。10月の結果でも食料(酒類除く)及びエネルギーの価格の寄与が2.2%ポイントと、総合指数3.7%上昇の半分超を占める状況は依然変わっていない。だが、欧米型コアでみた物価上昇率が+1.5%となったのは、消費税率を引き上げた2014年時点を除けば、1993 年4月以来であるのも事実である。日本のインフレ率の高まりは、日本が多くを輸入に依存する食料やエネルギーの価格上昇が主因で、国内の需給を反映した動きではない、とは言い切れない状況になりつつある。
図表1は1971年から現在までの日本のインフレ率を俯瞰している。日本のインフレ率は1972年あたりまで+5%から+6%の伸びで推移していたが、その後大きく上昇に転じ、1974年2月に総合で前年比+24.9%、欧米型コアで同+20.6%となった。この急速なインフレ率の高まりは、1973年10月の第四次中東紛争の勃発を受けた石油価格の高騰(第一次石油危機)ではなく、当時の日本銀行の不適切な金融政策(行き過ぎた金融緩和策)が主因である(なお、日本国内でこうした見解が形成されるきっかけとなったのは、先日亡くなられた小宮隆太郎氏の先駆的な研究による所が大きい)。そして1974年に日本は戦後初めてのマイナス成長を経験する。1978年末に第二次石油危機が生じて石油価格は再び高騰したが、1979年に就任した前川春雄日本銀行総裁の金融政策により、インフレ率の高進は最小限で食い止められた。その後、1980年代半ばから1993年あたりまで、日本のインフレ率は2%程度で概ね推移することになる。1990年初のバブル崩壊後の長期停滞および日本の不十分なマクロ経済政策の結果、1998 年以降、日本は1%未満のマイルドかつ長期に亘ったデフレを経験した。長期デフレの潮目が変わったのは第二次安倍政権の下で就任した黒田東彦総裁の金融政策(量的・質的金融緩和策)の貢献である。
ただし、図表にある通り、デフレではなくなったものの、0%台のインフレ率が長らく続いていた。今、こうした状況に変化が生じてきているという訳である。
先月のMonthly Economist Reportでは、グローバルなインフレ率の高まりの中で日本のインフレ率も2%を超えて推移する「インフレの時代」が成立する場合に、政府、日本銀行、そして日本企業がどう対応すればよいのかを論じた。もちろん、デフレが長期化した日本にあって、本当に「インフレの時代」が到来するかは異論のある所であろう。以下では、足元のインフレ率の動向を分析しながら、1970年代、1990年代の経済・物価動向を敷衍することを通じて、日本のインフレ率の将来について、筆者が考える3つの可能性を検討することにしたい。
続きはPDF版をご覧ください。
レポート全文(図版あり)はこちら
PwC Intelligence
――統合知を提供するシンクタンク
PwC Intelligenceはビジネス環境の短期、そして中長期変化を捉え、クライアント企業が未来を見通すための羅針盤となるシンクタンクです。
PwC米国の「PwC Intelligence」をはじめ、PwCグローバルネットワークにおける他の情報機関・組織と連携しながら、日本国内において知の統合化を推進しています。

本ページに関するお問い合わせ
関連情報


地政学リスクマネジメント対応支援
米国と中国の間での貿易摩擦や英国のEU離脱を巡る混乱など、地政学リスクのレベルが高まっています。日本企業にも、リスクマネジメントに地政学の視点が必要です。事業に対する影響の評価、リスクの定量化、シナリオ予測などの手法を用いて、地政学リスクによる損失の軽減や未然防止に向けた効果的・効率的な対策立案と実行を支援します。

サステナビリティ情報開示支援
サステナビリティの知見とサステナビリティに関する各国法規制や国際ガイドラインを熟知したメンバーが企業の情報開示を支援します。
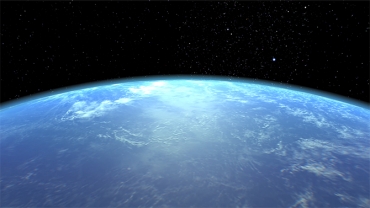
宇宙・空間産業推進室
PwCコンサルティングは、気候変動など地球規模の課題解決に向けて、「宇宙・空間」をリアルとデジタルの双方から俯瞰した視点で捉えていくことで、陸・海・空、そして宇宙における分野横断的な場づくりや関連産業の推進、技術開発、事業活動を支援しています。
