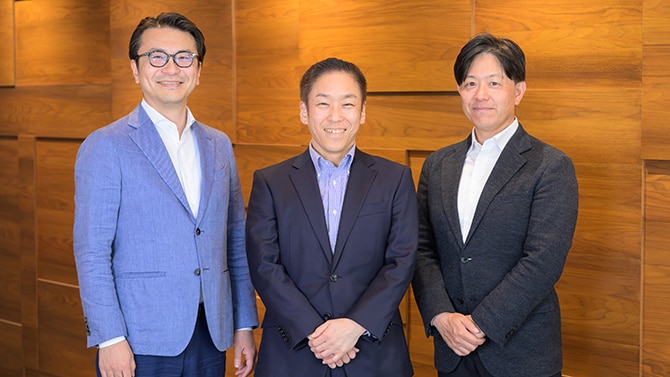{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
脱炭素化、分散化、デジタル化の波が加速度的に押し寄せ、日本のエネルギー業界は、従来の延長線上で未来を描くことが困難な「構造的転換点」に立たされています。PBR(株価純資産倍率) 1倍割れ、電力・ガス自由化後の収益構造の再設計、地政学リスクを背景としたエネルギー危機――こうした複合的な圧力が、同業界に戦略の再定義を突きつけています。もはや部分的な改善では立ち行かず、全社的な変革と経営資源の再配分が、将来の「生存条件」となりつつあることが現実です。この危機感を背景に、PwC Japanグループのプロフェッショナルが、グローバルな潮流と先進企業の動向を踏まえ、日本企業が取るべき具体的なアクションについて議論しました。非エネルギー分野への進出、事業ポートフォリオの再構築、M&Aやガバナンス強化などまで、日本のエネルギー業界各社が競争力を再定義し、新たな成長軌道を描くための視座を提示します。
登場者
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
片山 紀生
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
吉田 英史
PwC Japan有限責任監査法人 パートナー
熊田 崇史
※法人名、役職などは掲載当時のものです。
左から、熊田崇史、片山紀生、吉田英史
片山:はじめに、電力・ガス・石油などのエネルギー業界を取り巻く現状と変化、さらにはそこから浮かび上がる日本企業の構造的課題について議論したいと思います。まず、私から現状認識を共有します。日本は現在、エネルギー政策において以下3つの要素において高い水準での達成を求められています。
① エネルギーの経済性(Energy affordability)
② エネルギーの安全保障(Energy security)
③ 脱炭素化(Decarbonization)
これらは「エネルギートリレンマ」とも呼ばれます。例えば、安定供給を重視すれば火力発電への依存が高まり、脱炭素化が遅れる。一方で、脱炭素化を急げば再生可能エネルギー(以下、再エネ)への投資が必要となり、コスト上昇や供給の不安定化を招く――といったトレードオフの関係性です。
世界的に見ても、AIの急速な普及に伴うデータセンターや半導体工場の新設がエネルギー需要を急拡大させており、将来的なエネルギー不足が懸念されています。特に、エネルギー自給率が12~13%にとどまる日本では、この課題が一層深刻化する可能性があります。加えて脱炭素化の観点では、米国のトランプ大統領が2025年1月にパリ協定からの再離脱を表明し、バイデン政権下で進められてきたクリーンエネルギー支援策の大幅な見直しに着手しています。 特に、IRA(インフレ抑制法)に基づく電気自動車充電インフラや再エネ関連の補助金支出を停止し、多くのプロジェクトがキャンセル・遅延となっています。 この「トランプ2.0」における化石燃料回帰の政策転換により、洋上風力や太陽光発電の開発停滞も予想されています。
そうした中、日本では第7次エネルギー基本計画において、再エネ比率を2040年度までに40~50%へと大幅に引き上げ、再エネを最大の電源とする方針を掲げました。また、原子力発電の比率も見直し、脱炭素化と安定供給の両立を目指す方針としています。この第7次エネルギー基本計画について、熊田さんの見解を伺えますか。
熊田:再エネの最大化はエネルギー政策における重要な柱であり、そこに向けた投資の本格化は、日本企業にとって極めて重要な論点です。特に注視すべきは、米国の政策転換が国際的な投資環境に与える影響と、それに対して日本企業がいかに戦略的に対応していくかという点です。
再エネの最大化には多大な資金が必要であり、資金調達は最も重要な課題の1つと考えられます。加えて、会計的な観点からは、再エネ投資に対する減損リスクも無視できない要素です。こうした状況を踏まえると、脱炭素と安定供給の両立を目指す日本企業にとって、経営上の大きなチャレンジに直面していると言えるのではないでしょうか。
片山:エネルギー会社の財務面を見ると、PBR(株価純資産倍率)1倍を下回る企業が多く、資本市場からの評価という点で課題を抱えています。こうした状況を踏まえ、エネルギー会社にはどのような課題があり、今後どう対応していくべきかについて、吉田さんの意見を聞かせてください。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 片山 紀生
吉田:エネルギー各社のPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回るという状況の改善に向けては、当然ながら「収益性の向上」、「資産効率の改善」、「成長期待」に取り組む必要があります。財務的な観点では、収益性と資産効率を表現するROIC(投下資本収益率)の改善が重要であり、資金調達を最適にすることでROE(自己資本利益率)の向上も求められていると思います。
一方で、エネルギー会社には今後、脱炭素に向けた大規模投資が期待されています。ただ現実には、洋上風力をはじめとする再エネ関連のプロジェクトは、資材価格の高騰や「2028年問題」と呼ばれる建設業界の担い手不足などにより、建設コスト・工事進行の両面で制約を受けるはずで、大型工事を計画通りに進めるのは難しい状況になるでしょう。そうした環境下で、収益性、資産効率を改善しながら脱炭素化に向け再エネへ積極的な投資も進めなければならないという、ある種の矛盾を抱えているのが、現在の立ち位置だと思います。また、脱炭素に向け再エネ事業は成長領域であるべきですが、収益の予見性が厳しい状況下において、成長領域をどこに見出していくのかも非常に重要となっていきます。熊田さんに伺いたいのですが、PBRを改善させる観点ではPER(株価収益率)の改善も鍵となると考えます。また、財務的な資産効率の関係ではリース会計も影響があるのではないかと思いますが、どのように見ていますか。
熊田:リース会計の観点は、IFRS(国際会計基準)で先行導入されていたリース会計基準の日本版がいよいよ導入されますから、今後の財務的インパクトの検討は急務で、電力・ガス会社のみならず広くエネルギー会社においても重要な論点になっていくでしょう。例えば、PPA(電力購入契約)については、全量買い取りなど、契約の内容次第で電力購入企業が発電設備をオンバランス(貸借対照表に計上)しなければならない可能性があります。
ROICという観点からは、すでにリース会計基準を適用している海外のエネルギー会社の事例を見ると、オンバランス化されたPPA関連の資産によるROICへの影響が顕在化しています。ただし、リース会計による株価への影響はそれほどではなかったと言われています。これはステークホルダーとの丁寧なコミュニケーションが行われた結果と考えられます。日本企業としても、自社のPPAが海外企業と同様の構造である場合には、ROICへのインパクトが同様に現れることになります。そのため、PPAの構造を見直すのか、あるいはROICの捉え方自体を見直していくのか、加えてどのようにステークホルダーとのコミュニケーションを行っていくのか、さまざまな経営上の検討が求められると考えます。
また、株主価値の観点で言うと、吉田さんのお話のとおりPBRの改善にはROEに加えてPERにも着目すべきです。PERは、企業の将来収益や定性的な価値に対する投資家の評価が反映されるものですが、「日本企業のPERは総じて低い」と言われています。この大きな背景の一つとして、ステークホルダーへの情報開示不足が挙げられます。したがって、ROICやROEといった財務指標の改善やこれらの指標についての説明(例えば、新リース会計による影響の説明など)と並行して、特に非財務情報の開示を積極的に行い、PERの改善に注力していくことが重要な課題になると思います。
片山:会計基準の観点から見ると、日本企業もグローバルスタンダードに合わせていく必要があり、海外の競合他社と同じ土俵で比較・評価できるような情報開示が求められるでしょうね。実際に私たちも、財務戦略の見直しやリース会計への対応などのご相談をいただくケースが増えています。
また、投資家の目線に立つと、市場制度の度重なる変更により、国内エネルギー企業の収益の予見性が乏しくなっていることへの懸念が増していると感じます。事業者自身が予見性を持てないなかで、投資家が安心して資金を託すことは難しい。だからこそ、企業側が収益の見通しや株主還元について、いかに明確なメッセージを発信できるかが、今後ますます重要になってくると思います。
一方で、電力・ガス会社を中心とするインフラ企業の中には、「アセットライト」――資産を圧縮し、機動的な経営体制を目指す動きも見られます。これはある意味、リース会計とは逆の方向かなとも思います。この「アセットライト」という方向性について、吉田さんはどう考えますか。
吉田:そういう意味では、エネルギー会社のバランスシートのあり方についても見直すべきタイミングにきているのではないかと思っています。全ての資産を自社で抱え込むのではなく、資本コストをともに担ってくれる投資家と、役割とリスクを分担しながら資産効率を改善する――正確には、外部ステークホルダーとの役割分担を前提とした資産戦略に移行していくことが、これからの方向性として重要ではないでしょうか。その上で、エネルギー会社として果たすべき役割――例えば、脱炭素の推進や再エネの導入拡大に向けた主体的なポジション――を改めて定義し、戦略的に取り組む必要があると感じています。
また、ROICやROEといった財務指標は、あくまで「一時点」における、企業の「財務的な断面図」です。一方で、投資判断は一般的なLNG火力発電であれば稼働まで少なくとも5年以上、稼働してから耐用年数30年といった長期スパンを前提とするものであり、評価軸とのギャップが常に存在します。増加する電力需要と脱炭素という大きな潮流の中、長期的かつ多額の投資が求められる一方で、短期的なROICの改善といった課題も突きつけられている――こうした構造的な矛盾を抱えるエネルギー会社ができることとしては、自社単独で全てを抱え込むのではなく、外部パートナーと役割やリスクを分担する体制を築くことではないかと思います。その上で「自社の価値とは何か」「どこに競争力を発揮できるのか」といった点を見つめ直して進めていくことが、これからの経営戦略において考えるべきポイントになると思います。
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー 吉田 英史
熊田:長期投資の回収リスクと、それをいかにパートナーと分担するかという観点で言うと、話はややそれるかもしれませんが、「石油・ガスの上流事業」と構造的に似た点があると思います。例えば、上流事業では試掘などが失敗するリスクがあり、加えてプロジェクトの総投資額が非常に大きいため、1社単独ではなく複数社でパートナーシップを組んで進めるのが一般的です。その際には30~40年単位の長期的な視点で、「どの程度の回収が可能か」「その回収見通しの確実性や予見性をどれだけ関係者間で共有できるか」が、極めて重要な判断軸になります。特にリード役(オペレーター)となる企業が、その投資の妥当性や収益性について、他のパートナー企業に対して丁寧に説明し、理解を得ていくことが欠かせません。
一方、電力・ガス事業においては石油・ガス開発でいうところ「埋蔵量」に相当する「収益回収見通し」の情報を、外部に対して明確に開示することは困難です。そのため、パートナーや投資家に対して丁寧にどのように説明するかが今後の信頼構築における重要なポイントです。吉田さんが話したとおり、ROICやROEはあくまでも一時点での「財務的な断面図」に過ぎません。むしろ長期の資本投下に対して、「どのようなリターンを見込んでいるのか」という、その説明、開示が必要で、それが企業の信頼性や透明性を高めていくことになるのではと思っています。
片山:2人の話から、適切なパートナーと組んでリスクシェアしながら、「『稼ぐ力』や『資本効率性(ROIC、ROE)』をどのように上げていくのか」という視点で見ていくべきだということ、また、中長期視点でしっかりとステークホルダーとコミュニケーションを取りながらアカウンタビリティを果たしていくといったことがポイントになるということを再認識できました。
これまでの議論にもあったように、「稼ぐ力」を高めて「資本効率(ROIC、ROE)」を改善していくには、電力・ガス会社として成長戦略にしっかり取り組んでいく必要があります。具体的には、主に次の3つの方向性があると考えます。
1つ目は、国内事業でのシェア拡大。以前は「人口減少によりエネルギー需要は伸びない」と考えられていましたが、生成AIの普及に伴ってデータセンター需要が急増、これに対応したエネルギー供給が喫緊の課題となっています。また、経済性の確保が難しいとは言われるものの、再エネ事業開発をどうしていくのかといったことも検討しなくてはなりません。
2つ目は、アジア市場への進出。既に、ベトナムの水力発電、インドネシアの再エネ事業、タイでの太陽光発電や地下変電所の建設など、日本企業の知見を生かした展開が進んでおり、今後も大きな成長余地があると見ています。さらに、LNGの需要も大きく、アジアの新興需要国ではLNGの導入が進んでいます。これにより、エネルギー供給の安定化と脱炭素化の両立が期待されます。
3つ目は、エネルギーの周辺領域への事業拡大。例えば、通信、不動産、モビリティ、EVインフラといった分野への進出を通じて収益源を多様化し、ポートフォリオの分散を図ることは、ROICやROEの観点からも有効です。
こうした観点を踏まえて、今後の投資や事業展開においてはM&Aを含めて変革への一歩をどう踏み出すかが重要になります。この点に関して、日本の電力・ガス会社がどのようなスタンスを取るべきか、意見をください。
吉田:当然ながらPBR、株価を意識した時、「エネルギー会社の成長領域はどこにあるのか」ということは、常に投資家から問われることです。振り返ると、電力セクターでは、2016年の電力小売全面自由化で、家庭向けを含む低圧分野にも新規企業参入が進み、既存の電力会社はシェアを奪われる立場となりました。「こうした縮小局面をどうカバーし、成長を描いていくか」という議論は、電力会社ではかれこれ10年近く続いています。これまでの動きを見ると、例えば成長が見込まれる海外のガス火力発電市場へ進出する、あるいは電力に近接したインフラ領域(通信や不動産)へ事業展開するといったことが行われてきました。今後も電力会社にとって、通信や不動産といった非電力領域は成長の余地がある注目分野となるでしょう。
一方で、通信や不動産などの非電力領域は、電力会社にとって本業ではないため課題も大きい。果たして、「これらの分野で業界トップクラスの企業に匹敵するような収益性を確保できるのか」、「そうした事業展開を支えるM&A戦略や組織的なケイパビリティは備わっているのか」といった点は、マーケット(投資家)から厳しく見られることになります。とはいえ、電力会社には地域に根ざした信頼とブランド力がありますので、これらのアセットを最大限に生かして、有意な立ち位置から、非電力領域を広げていく可能性は十分にあると考えています。
熊田:「Transact to Transform」、M&Aを通じた変革の実現においては、エネルギー会社の周辺領域への事業拡大は不可欠な方向性です。ただし、エネルギー会社がそれぞれの中核とする石油・電力・ガス以外の領域に進出する際には、組織上の運営課題が生じる可能性があります。これまでは、エネルギー会社が中核事業として行っていた事業に対して、比較的「閉じた文化」の中で展開してきたと思われます。中核事業領域外の事業への拡大は、異なる業界・企業文化や価値観を持った人材が加わることになるため、経営者の方には「求心力を維持して、文化の異なる領域を伸ばすのか」または「遠心力を働かせて、現場に自由度を持たせるのか」というマネジメントの方針を問われることになります。併せて、それぞれの事業に携わる経営者の業績評価のあり方、さらにはガバナンスの設計も重要な論点となっていきます。
守りのガバナンスと攻めのガバナンス、それぞれの性質をどうバランスよく組み合わせるか――成長するにあたり、どのようにガバナンスを設定していくかといった点も大きな論点になってくると思います。 中核事業領域以外への本格進出は、エネルギー会社にとって極めて大きなチャレンジになりますが、こうした注意点があることを知っておくことは必要です。
PwC Japan有限責任監査法人 パートナー 熊田 崇史
{{item.text}}

{{item.text}}