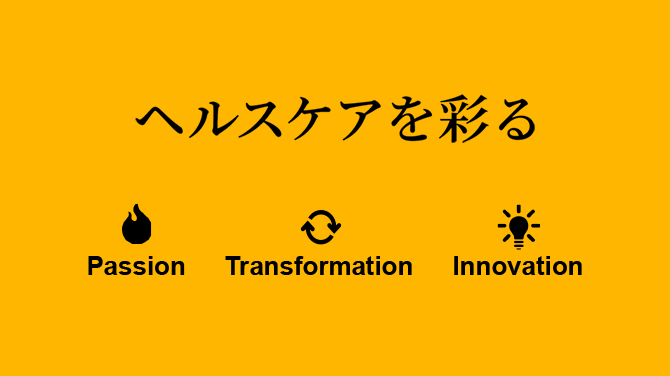{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2022-04-22
医師や看護師などの医療従事者、最新の知見や技術を持つ研究者、医療政策に携わるプロフェッショナルなどを招き、その方のPassion、Transformation、Innovationに迫る対談シリーズ「医彩」。第8回は東北大学大学院医学系研究科医学情報学分野の教授である中山雅晴氏をお迎えしました。中山氏は循環器内科医師と医学情報分野の教授という二足のわらじを履きながら、臨床現場にとって有用な病院情報システムや地域医療連携システムの開発などに注力しています。激務をこなしながら、臨床データの活用拡大に情熱を注ぐ中山氏の日々の取り組みや、今後の展望について伺いました。(本文敬称略)
東北大学大学院 医学系研究科 医学情報学分野 教授
中山 雅晴氏
PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー 水野 光
PwCコンサルティング合同会社
シニアアソシエイト 粟津 恵里
※所属法人名や肩書き、各自の在籍状況については掲載当時の情報です。
水野:初めに、中山先生が医学情報学分野に携わるようになったきっかけを教えてください。
中山:もともと私は循環器内科の医師で、大学病院では狭心症や心筋梗塞などの治療チームに属していました。そこで実感したのは「データがうまく活用されていない」ことでした。大学病院には研究や診断に役立つデータが多くありますが、それらを統合するためには異なったシステムから個々の努力で収集せざるを得ないことが多く、多大な労力を要します。そのため、循環器内科患者さんのデータベースを構築しながら、病院情報システムを管理するメディカルITセンターに多くのリクエストを出していたのですが、「そこまで関心があるなら自分でやってみたら」と言われ、循環器内科の医師をしながら病院情報システムにも関わるようになり、その後しばらくして当時の院長に電子カルテの導入を進めるよう言われ、医療情報の仕事がメインになりました。
水野:医療情報部門は大学病院の中でどのような役割を担っているのですか。
中山:個々の施設によって異なるとは思いますが、自分としては電子カルテの使い勝手をよくすることと、同時に臨床研究を円滑に進めるためのシステム作りを意識していました。具体的には、異なるシステムから抽出した患者情報を集約するデータベースの構築、電子カルテや各診療科データとの連携基盤の確立などです。
水野:一言で「臨床研究や治療にデータをうまく活用する」と言っても、その幅は広いですよね。基本的な質問ですが、データを活用することで患者さんはどのようなメリットを享受できるのでしょうか。
中山:ある治療を選択する場合、臨床試験の結果が大きく働きます。例えば薬でいえば、Aという薬とBという薬を投与された患者さん達を比較して、A群のほうが有意に生存率を改善されるならばAを投与することになります。しかしながら患者さん個人にとっては、例えばその効果の出る確率が90%であったとしても、薬の効かない10%に入ってしまうこともあります。我々からすると確率90%なら10人中9人には役に立つということで、自信を持って投与しますが、それでも効かない方に入ってしまった患者さんにとっては「90%の確率で効果がある」と言われても、自分に効かなければ何の意味もありません。その差をもう少し埋めることができないかを普段考えています。
大量の医療データの活用やITの力を駆使することで、今までにないエビデンスを構築すること、さらに、目の前にいる患者さんからより詳細な情報を得ることで、正確な効果やリスクを明らかし、患者さんにより的確な情報を提供したいというのが、医療情報学に注力する私のモチベーションでありパッションです。
電子カルテの導入を担当した時に、「先生は電子カルテが好きなんですね」と言われたこともありますが、電子カルテやデジタル化そのものが物凄く好きというわけではありません。むしろ、自分がやりたいのは目の前の患者さんを治すことであり、電子カルテやデジタル化を進めることは、データを収集や連携、活用することを容易にし、最終的には患者さんの治療に役立てられるという動機があるからです。電子カルテの導入はそのための手段と思ってやっていました。
水野:病院におけるITというと、電子カルテが真っ先に思い浮かびます。電子カルテを導入すれば、容易にデータの収集・連携・活用が可能となるのでしょうか。
中山:電子カルテを導入したからといって、治療に関するデータを簡単に活用できるわけではありません。例えば、病院内にはさまざまな診療データが保管されていますが、このデータはシステムごとにいわばサイロ化されており、連携させてデータベースを構築するには相応のコストがかかります。また、病院をまたぐデータ連携についても、各病院の電子カルテのデータベースの構造やフォーマットが異なるため、やはり簡単には連携できません。
粟津:今後の医療を考えると、病院をまたいでデータを統合し、解析していくという取り組みも求められると思いますが、医療現場ではどのように取り組んでいるのでしょうか。
中山:日本では2006年度に「厚生労働省電子的診療情報交換推進事業」がスタートしました。その成果が「SS-MIX(Standardized Structured Medical Information eXchange)」です。これは、全ての医療機関を対象とした医療情報の交換・共有による医療の質向上を目的としたもので、異なるベンダーの病院情報システムに格納されているデータを共通フォーマットで保存するというものです。現在SS-MIXはバージョン2で、標準化ストレージでは患者のIDや日付を軸に、基本情報や検査情報などをフォルダ階層で管理しています。
ただし、循環器内科の医師の立場からすると、採血結果や投薬履歴といった情報だけでは患者さんの詳細がわかりません。ですから、心電図や心臓超音波、カテーテル検査結果といったデータも交換・共有するにはどうすればよいかを考えました。
水野:そのようなデータは共通フォーマットとして保存されていなかったのでしょうか。
中山:そうです。メーカーごとに項目名や単位などが異なっていました。こういったフォーマットを整備するためには学会の承認が重要と考えました。そこで日本循環器学会の理事長に直談判をしました。最もメジャーな学会が了承すれば、他の学会も承認してくれるだろうと考えたからです。
最終的に、日本循環器学会理事会が「SS-MIX拡張ストレージにデータ出力できる仕組みを作成していく」という方針を承認してくれました。これを受けて、日本不整脈心電学会や心エコー図学会など複数の学会がこの方針に協力頂いています。これによりデータ出力標準フォーマットガイドライン「SEAMAT(Standard Export datA forMAT)」を策定することができました。
粟津:電子カルテへの情報集約では、QRコードを使ったシステムを開発したと伺っています。
中山:はい。医師が患者さんを診察する際、デバイスを使った問診ツールに入力させるケースがありますが、そのデバイスから直接電子カルテにデータを取り込めるようにはなっていないことが多いのですね。なぜならセキュリティ上の懸念から、電子カルテや病院情報システムは閉じたネットワーク内にあるからです。
しかし、問診データを電子カルテに取り込みたいという要望は以前より多くありました。そこで作ったのがQRコードを使ったシステムです。消化器内科の先生が問診アプリを開発し、そのデータをQRコードに変換します。一方、電子カルテの方はQRコードリーダーを用いてそのデータを読み込み、テンプレートとして電子カルテに保存する仕組みを構築しました。これにより、問診データは診療録になりますし、医師に戻せば研究データにもなります。医師側も病院側にとってもメリットのある仕組みとなりました。
この方法を発表したら、「コストをかけることなく自分たちで作成したことがいちばん素晴らしい」と評価されました。同じような課題を抱えている現場は多かったのですが、コストの問題で二の足を踏んでいる。QRコードを使ったことは「コロンブスの卵」に見えたのかもしれません。
粟津:さまざまな制約がある中で手持ちの技術と知恵を駆使して課題を解決する。現場におけるトランスフォーメーションの好事例だと思います。
水野:トランスフォーメーションというと、現在、日本では「Society 5.0」*1の実現に向け、さまざまな取り組みが進められています。医療業界ではSociety 5.0をどのように捉えているのでしょうか。
中山:これまで紙カルテばかりだったものを電子化したという意味においては、少なくとも牛・馬を使っていた農耕社会のSociety 2.0から脱却していると思います。ただし、現実は紙を電子化しただけというケースも少なくありません。ですから医療業界において「Society 5.0を実現する」にはまだまだ進めるべき問題があり、現在はSociety 3.0からSociety 4.0の入り口にいるところだと思います。
粟津:Society 5.0では分野横断的なデータプラットフォームが存在し、多分野間のサービスがワンストップ化されるという世界が描かれています。医療業界にこうした世界を当てはめてみると、社会福祉や交通などの業界が持つデータとの相互連携が考えられます。例えば、病院を予約したら自動的にタクシーが手配され、必要に応じて通院支援の福祉サービスが受けられるといった具合です。先生は将来こうした方向に医療データが役立てられるようになるとお考えですか。
中山:概念としてのSociety 5.0は目指すべき姿だとは思います。しかし実際問題として、いくつもの乗り越える課題があります。電子カルテでしか実現できないようなサービスを患者さんに提供するために、今まで以上の機能やサービスを拡充し、電子カルテを成長させていく必要があります。
粟津:電子カルテの発展・成長にむけて、具体的にどのような取り組みが動いているのでしょうか。
中山:例えば、東日本大震災の際にさまざまなデータが消失した教訓から、宮城県では各医療機関や薬局などから患者さんのデータをバックアップとして保存するために地域医療情報連携ネットワークを構築するプロジェクトが立ち上がりました。最初は関わってなかったのですが、紆余曲折あって私も途中から関わるようになりました。お陰様で、そのネットワークは今でも続いていますが、地域医療情報連携ネットワークシステム全体に関しては、その課題が色々と指摘され、とりわけ、長く維持することの困難さが問題となっています。最近は、むしろPHR(Personal Health Record)に対する期待が大きくなっています。PHRは普段個人が利用しているスマートフォンなどから日々の健康に関するデータを記録できます。医師側からみれば、こうしたデータを電子カルテに統合することで、治療の判断材料が増えるというメリットが期待されています。
粟津:そうしたデータを電子カルテ等に取り入れるには、標準化された規格が必要ですよね。
中山:はい。そこで注目されているのが「FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)」です。FHIRは医療情報交換を目的とした実装しやすい新標準規格です。FHIRのメリットはRESTful APIを利用してウェブ上でデータのやり取りができることであり、データ形式もJSONやXMLなど人間が理解しやすくなっています。FHIRが普及することで、今まで参入していなかった様々な企業が医療業界向けアプリケーションを容易に開発できるようになると期待しています。また、医師などユーザーの視点を取り入れた開発も進みやすくなるのではないかと思います。と言いますのも、ユーザーとシステムベンダーとの間で認識のずれがあることは多く、システム開発をする際には、意見収集や仕様策定、実際の動きの確認など、多くの労力を割く必要があります。もう少し、そのやりとりを効率的にできないかと常々思っていて、ちょっと愚痴めいてしまいますが、私はこの状況を「二人羽織」と表現しています。よりダイレクトにユーザーの意見を反映したモノづくりができることが進むことを期待しています。
また、それはプロジェクトにおいても同じで、何か新しいことを始めるときにはネゴシエーションがとても重要です。色々な意見を聞くことはもちろん大変重要ですが、なかなか解決志向でない姿勢があったりすると事態が遅々として進まなくなります。こうしたフラストレーションを抱えているのは皆さん共通にあると思います。
水野:「現状でいいじゃないか」と考える人に対し、行動変容を促すことは容易ではありません。しかし、イノベーションを起こすためには、超えないといけないハードルです。周囲の行動変容を促すために心がけていることはありますか。
中山:危機感を共有することも一つのやり方かと思います。私は「慣性の法則」と呼んでいますが「現状を変えたくない力」はかなり強固なので、人々の行動変容を促したりするにはものすごいパワーが必要です。しかし、このままの状態が続けば、何が起こりうるかを明らかにして、「本当にこのままでいいのか」ということを問うことが必要かと思います。医療情報のデジタル化やデータ活用において、日本はまだまだやるべきことがありますので、危機感を共有し、正しく行動変容ができれば、一気に変化を起こせる可能性があると期待しています。
粟津:最後に今後の展望を聞かせてください。近年、産学連携の必要性が指摘されています。先ほど「概念としてのSociety 5.0は目指すべき姿」と仰いましたが、どのようなビジネスの可能性が考えられるでしょうか。
中山:外国の方と話をすると、ビジネスモデルについて聞かれます。その場では「お金を稼ぐDNAを持っていれば大学で働いていません」と冗談めかして言ったりもするのですが、大学で取り組んでいるようなプロジェクトをビジネス化することはとても大事だと考えています。
日本においてパイの奪い合いだけでビジネスをする時代は終わりました。これからは大学や企業がそれぞれ持っている特性を活かしつつ、新たなことに挑戦する必要があります。そのためには大学と企業が垣根を越えて連携し、コミュニケーションをしていくことが重要だと考えます。
ただし、我々が研究の軸足をビジネスに移してしまうと、上手くいかないケースも出てきます。研究とビジネスのバランスを取りながら、新しいアイデアを創出できるようにならなくてはなりません。そのためには、両者の考え方を理解したうえで、間に立ってコミュニケーションを円滑にするコンサルタントのような方も必要だと思います。
水野:私たちコンサルタントはプロジェクトを鳥瞰し、その全体像を描きます。しかし、そのプロセスで現場の困りごとを見落としていることに気付かずに絵を描いてしまうこともあります。ですから、先生方と密にコミュニケーションをとってお話を伺い、同じ目線でビジネスモデルを考えられるようにすることが、PwCに求められるアクションであると再認識できました。本日はありがとうございました。
*1 狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会という意味で、政府の第5期科学技術基本計画(2016年1月)において初めて提唱された考え方。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}