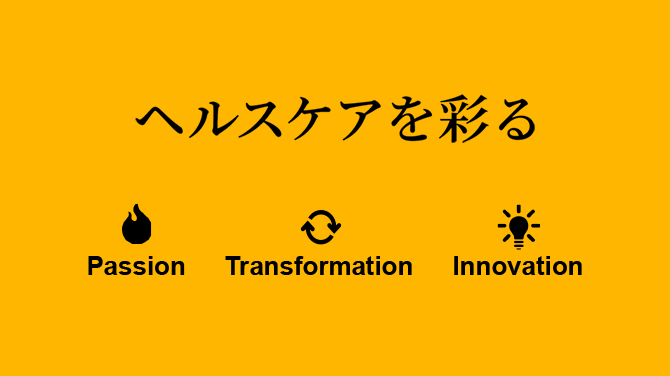{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2022-10-18
医師や看護師などの医療従事者、最新の知見や技術を持つ研究者、医療政策に携わるプロフェッショナルなどを招き、その方のPassion、Transformation、Innovationに迫るシリーズ「医彩」。第10回は北海道大学 大学院理学研究院 化学部門 分析化学研究室 准教授の龍崎奏氏をお迎えしました。
龍崎氏はナノバイオデバイス、有機エレクトロニクス、マテリアルサイエンスといった領域で研究を重ね、現在はライフサイエンス系分野で起業に向けた準備を進めています。しかし、「大学発の起業」にはさまざまな壁と課題があり、一筋縄ではいかないのが現実です。では日本の大学組織にはどのような構造的課題があるのでしょうか。その課題を克服し、イノベーションを起こすには何が必要なのか、PwCコンサルティング合同会社のメンバーがインタビュアーとしてお話を伺いました。(本文敬称略)
※法人名、役職などは掲載当時の情報です。
インタビュアー:
現在、龍崎先生は大学における技術開発の活性化に尽力していらっしゃいます。そのパッションの源流を教えてください。
龍崎:
一口に言えば「大学を通じ、日本にとってプラスになることがしたい」という思いです。
私は東京工業大学で原子核工学を専攻していました。その時にIAEA(国際原子力機関)でインターンを経験し、さまざまな国の方々との仕事を通じて国際性や多様性の観点から国際経験が重要であることを痛感し、東京工業大学卒業後はデンマークにあるコペンハーゲン大学の化学専攻およびニールス・ボーア研究所(Niels Bohr Institutes)の博士研究員としてキャリアをスタートさせました。その時の経験が、現在の活動に進むターニングポイントとなったのです。
インタビュアー:
デンマークは幸福度が高い国として知られています。世界で初めて同性婚が法的に認められたり、留学生を積極的に受け入れたりと「ダイバーシティの最先端」というイメージがあります。博士研究員時代にはどのような学びがありましたか。
龍崎:
留学中はあらゆるバックグラウンドを持った方たちと議論する機会に恵まれました。その時に痛感したのは自分の幼さです。
例えば、こんなことがありました。中東から留学している学生と宗教に関する議論をした時のことです。外国で宗教の話はタブーなのですが、お互い気心が知れていたので、「なぜ宗教観の違いで内戦(紛争)にまで発展するのか。無宗教の自分には理解が難しい」と質問しました。その時に返ってきたのは「日本では年間3万人ぐらい自殺する。それもある意味内戦だよね」という答えです。私は彼が他国の自殺事情を知っていることにも、自殺と戦死を同等と見なす考え方にも驚き、自分の固定観念が揺さぶられるような感覚を覚えました。
このようにサイエンスのレベルが高いだけでなく、人間力の高さを感じる経験が何度もありました。
インタビュアー:
外国での学びが日本を俯瞰するきっかけになったのですね。
龍崎:
はい。特に日本の教育環境を客観視できるようになりました。そんな折に東日本大震災が発生し、「自分も日本に対して何かできることはないか」と考えて帰国したのです。
「日本にプラスになること」を考えた時、大学教員という職業は非常に魅力的でした。天然資源の乏しい日本にとっての資源は、科学技術であり人材であると考えています。大学は科学技術に関する研究を行い、そして学生という若手人材を育成するための組織です。
日本にとっての資源である科学技術と人材の双方に関わる大学教員という職に就くことで、こんな自分でも少しは日本に対して何か貢献できるのではないか、と思い至り、大学教員になることを決めました。
北海道大学 大学院理学研究院 化学部門 分析化学研究室 准教授 龍崎 奏氏
インタビュアー:
上述のお話を踏まえると、志を持って大学教員としてご活躍されていたと思いますが、理想と現実のGAPを感じたことはあったのでしょうか。例えば、近年、日本の大学は研究の観点から国際競争力の低下が指摘されています。この点はどのようにご覧になっていますか。
龍崎:
正直に申し上げると様々なGAPや課題を感じて来ました。日本のどの国立大学も、海外のトップ大学と比較すると、懐事情は厳しく、国が掲げる「ノーベル賞級のイノベーション創出の基盤となる基礎研究の強化」「社会を変革する力と意欲を持った人材の輩出」「産学連携や大学発ベンチャー創出による産業構造改革」などの目標を実現させるための体制やシステムに課題があり、結果的に国際競争力が低下したと言われています。例えば、基礎研究強化に向けたボトルネックとして、次の様なものが挙げられます。
例えば国立大学の場合、国からの補助金である運営費交付金だけでは教職員全ての人件費や研究費を賄うことができないため、事務補佐員、技術職員、ポスドク、特任教員の方たちの人件費や、学生の学会参加費などの教育に関わる経費の多くは競争的資金である「研究費」から捻出されます。つまり、研究費が無くなると同時にこうした方々を雇用することは難しくなるため、プロジェクト毎に研究員や技術職員が変わってしまう場合があり、その都度、OJTを行う必要があります。また、研究費が獲得できないと学生の卒業研究も滞るため、教育にも影響します。さらに、事務補佐員がいない研究室では教員の事務仕事が増えるため、研究に使う時間が減ってしまいます。
また、労働契約法によって研究者は10年目で雇い止めとなる可能性があるため、その間に成果を出し、任期なしのポジションを獲得する必要があります。そのため、短期的に成果の出やすい研究テーマを選ぶ傾向があり、若手研究者は時間のかかる挑戦的な基礎研究はし辛い環境にあると言えます。
インタビュアー:
そうした構造的な課題は、組織の中にいなければ見えてこないですね。
龍崎:
また、研究を実施すること自体の課題に加えて、実施した研究を世に出す部分にも沢山の課題があると感じています。例えば、産学の連携が非常に難しいことが挙げられます。
産学連携では、大学と企業が連携することで大学の研究成果を実用化することを主な目的とする場合が多いのですが、大学教員が連携先の企業のために働いているような構図になってしまうことや、単純に企業への技術流出になってしまう場合も少なくありません。そのため、知財の扱い方やロイヤリティに関して大学と企業間で協議を重ねますが、必ずしもwin-winな条件がある訳ではありません。これは産学連携破綻の典型的なパターンと言えます。
インタビュアー:
なるほど、日本の国力を高めるためには科学技術や研究が不可欠ですが、そこに向けては、大学の研究力自体の向上に加え、事業化、つまり研究を世に出す部分に関する課題も見えてきたということですね。これらの課題を抱えながらも、高度な研究を実施・事業化していくためには、どのようなトランスフォーメーションが必要であるとお考えですか。
龍崎:
そうですね、色々あると思いますが、主に4つのポイントを念頭に置いて、研究や教育に取組むことが重要だと考えています。
・学生に研究を指導するだけでは不十分
・日本における科学技術の意義を教育する
・「産業にとって有益か」の視点で戦略的研究を行う
・「Made in Japan」を活用する
過去、大学教員は専門領域に特化して教育を主軸にしてきましたが、今後はそれだけでは不十分に思えます。現代の産業構造の観点から、専門的な知識だけでは不十分で、点と点を線で結ぶ力も重要であることが度々指摘されています。
そのため、単純に卒業研究を通じて専門性を学ぶだけでなく、「それが産業にどのように繋がっているのか」といった視点で考え、学ぶ意義を教えることも大切だと考えています。そして、日本にとって科学技術がいかに重要な資源であるかを理解してもらいたいと考えています。
また、少し前までは化学科を卒業した学生の殆どが化学メーカーに就職していたと思いますが、最近は必ずしもそうではありません。実際、私がこれまで見てきた学生は、ゲームメーカーや外資コンサルタント会社など様々な分野に就職していきました。つまり、化学科の教員であっても様々な業種や業態を理解し、それを踏まえた上で人材育成に関わっていく必要があると思います。
大学は社会に人材を輩出する最後の教育機関なので、その時代時代にあった教育をしていくことが大切です。そういった教育の先に、「日本にプラスになること」をしてくれる人材が生まれると考えています。
また、研究の事業化の観点から、研究意義を明確にすることが研究者に求められています。大学は自由な発想に基づいて様々な研究が行える機関です。そのため、何の役に立つのか分からない基礎研究もあります。実はそういった基礎研究はとても大切で、そういった研究が後に大きなイノベーションをもたらすことがあります。そのため、基礎研究は絶対にやめてはいけません。しかし、税金が投じられている以上、研究成果を産業に繋げて社会に還元していくことも大切です。最近は課題解決型研究として、産業やSDGsの観点から戦略的に研究することも求められています。大学の研究者は学部学科に関わらず、この二つの観点から基礎研究と応用研究の両方を行うべきであると思います。そして、「Made in Japan」の科学技術を構築し、それを活用することで「日本にプラスになること」に繋がっていくと思います。
これまで、大学教員は大学の研究や教育の中で様々な取組を実践してきました。そして、近年更なるトランスフォーメーションとして、大学発ベンチャーも重要視されており、私自身も起業に向けて取り組んでいるところです。
インタビュアー:
それは興味深いですね。龍崎先生はどの様なビジネスを検討しているのでしょうか。
龍崎:
血液検査でがんを発見する技術に関する研究をしています。大まかに説明すると、がん細胞から血液に漏れ出した微粒子「エクソソーム」の表面分子を測定することで、体内のがんを検出する技術です。エクソソームは直径100ナノメートルと非常に小さいため、表面分子を計測することは簡単ではないのですが、これらの情報を正しく計測することで、がんを検出するだけでなく、がんの種類も見極められると期待されています。そのため、がん診断技術としてこの技術が有用であると考え、研究開発を進めています。
インタビュアー:
がんは種類ごとに検査方法が異なりますから、1回の血液検査で済むのは画期的です。
龍崎:
低料金で簡便、かつ大きな痛みを伴わない検査であれば、グローバルで普及すると考えています。がんに罹患する人は世界中で増加しており、それに伴って市場も拡大しています。世界におけるがん診断市場が2028年までに28兆円規模に成長するとの予測もあります。現在の日本国内の同市場規模が8,900億円ですから、この技術が実用化されれば、日本にとっても大きなメリットになると考えています。
インタビュアー:
実用化に向けた歩みは順調ですか。
龍崎:
はい……と言いたいところですが、ここにも課題があります。それはマネタイズまでの道のりが遠いことです。ライフサイエンス系の事業を立ち上げる際には、厚生労働省の認可を受けなければなりません。これには時間がかかりますから、認可が下りるまでの間にどのようにマネタイズするかは大きな課題です。
もう1つは特許取得までの道のりです。まず、公的資金の研究費(直接経費)では特許出願料などの特許関連経費を計上できないケースがあります。
そのため特許の出願は大学の関連部署に依頼するのですが、大学の財源も限りがあるため、全ての知財を出願できるわけではなく、審査を通ったもののみが出願されます。大学によっては厳しい審査になります。
そして、大学から出願をしてもらったとしても、大学が特許出願の費用を負担するので、特許の権利は大学側に譲渡しなければなりません。つまり、自分たちが研究開発した特許でも、その権利を所有するのは大学であり、開発に携わった研究者(発明者)がその技術を使う時には大学とライセンス契約をする必要があります。さらに言えば、大学側がその特許を他の企業と独占契約をしてしまえば、我々はその知財を使うことはできなくなってしまいます。
また、国際出願(PCT出願)の場合は特許関連経費が非常に高額であるため、出願することがさらに難しくなります。
インタビュアー:
それは問題ですね。特に1点目についてはヘルスケア領域のベンチャーの皆さんとお仕事をする中で強く感じます。他の業界と違って、この業界ではどんなにいい製品があっても、薬事申請が通らないとビジネスが出来ないため、数年間は売上が立たない期間が発生してしまいます。そのため、資金の必要性がある一方、VCも投資をし辛く、資金繰りが苦しくなってしまいがちです。そのような企業に向けて、我々も今後支援に力を入れていきたいと考えています。
他に、民間企業と接点が増えていく中で、どんな点を今後改善していくべきだとお考えでしょうか。
龍崎:
最近感じているのは、「起業を目指しています」と言って企業の方にお目にかかると、「大学教員」ではなく「企業人」として扱われることです。それは当然なのですが、私たちはコンサルタントの方が描くようなビジネスロードマップや詳細な事業計画の立案には慣れていません。その点をご理解いただかないと、話がかみ合わずプロジェクトが停滞します。私たち研究者は、どちらかというとスティーブ・ジョブズではなくスティーブ・ウォズニアックなので、研究者とビジネスマンを上手く仲介することが大切であると感じています。そうした部分をPwCのようなプロフェッショナルにご支援いただければありがたいです。
また、先ほどお話し頂いた通り、VC側に大学の技術を十分理解できる人材が揃っておらず、投資判断がつかないがゆえに、なかなか医療系のベンチャーに出資が集まらない側面も確かにあると思いますので、VC側にも理系の博士号を持った人材の確保も今後必要なのでは、と考えています。
インタビュアー:
仰る通りですね。大学側ではビジネスの知識が、民間側では技術に関する知識が足りていないのかもしれません。今後は、教育や人材の雇用等を通して、お互いの欠けている部分を補っていく必要がありそうです。
龍崎:
まだまだ始まったばかりですが、大学教員兼起業を目指す立場の人間として、大学(研究)とビジネス(経済)の隔たりを乗り越える挑戦にこれからも取組んでいきたいと思います。また、今日お話しさせて頂いた通り様々な課題がありますが、そういった中でも素晴らしい研究成果を出し産学連携を実現されている先生方もいるので、そういった先生方を見習い、現状に言い訳することなく邁進していきたいと思います。
インタビュアー:
大変な挑戦だと思いますが、わくわくしてきますね。大学発ベンチャーが開発する技術は、ゲームチェンジを起こしたり、大きく世界を変える可能性を秘めています。本日のお話にあった事業計画の作成や特許取得等に関わる課題はPwCでもご支援できることがたくさんあると考えています。
我々としても大学発ベンチャーとのコラボレーションはとても刺激的ですし、学びがありますので、今後機会があれば、ぜひご一緒させていただければと思います。本日はありがとうございました。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}